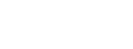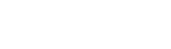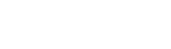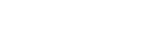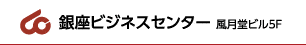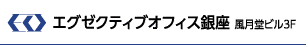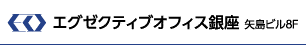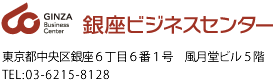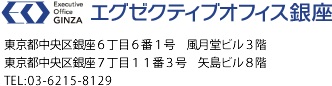目次
1.働き方改革推進支援助成金の概要
「働き方改革推進支援助成金」とは、働き方改革を推進する中小企業が、労働時間の短縮や休暇取得の促進など、従業員が働きやすい環境を整える際に、その取り組みにかかる費用の一部を国が助成する制度です。
中小企業の経営者にとって、従業員が安心して働ける環境を整えることは、生産性の向上や人材確保の観点からも非常に重要な課題です。しかし、労働環境を改善するためには多くの場合、設備の導入やシステムの整備、人材育成のための研修など、多くのコストが必要になります。
そのような負担を軽減し、中小企業が積極的に労働環境改善の取り組みを進められるように支援することが、この助成金制度の大きな目的です。
具体的には、次のような取り組みが支援の対象となります。
- 長時間労働の是正
- 年次有給休暇の取得促進
- 勤務間インターバル制度の導入
- 労務管理用設備・機器・ソフトウェアの導入
- 労働者および管理者向けの研修・コンサルティングの実施
この助成金の対象となるのは、労災保険の適用を受けている中小企業およびその企業団体です。中小企業の定義は業種ごとに異なりますが、例えば製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業では資本金5000万円以下または従業員100人以下など、企業規模によって定められています。
また、この助成金制度にはいくつかのコースが設けられており、自社が抱える課題や取り組みたい内容に応じて最適なコースを選ぶことができます。具体的なコースの違いや特徴については次の章で詳しく解説しますが、業種や規模、目的に応じて柔軟に選択できる仕組みとなっています。
さらに、この助成金は、原則として取り組みに要した費用の約75%(一部の小規模企業は80%、団体は100%)を補助するという大変魅力的な内容になっています。企業の負担を大幅に軽減しながら働き方改革を実現できるため、多くの中小企業が利用している制度です。
働き方改革を検討しているが、予算面でなかなか踏み切れない、あるいは具体的な制度の導入方法がわからないという中小企業の経営者にとって、この助成金は非常に役立つ制度です。次章以降では、具体的なコースや支給対象となる取り組み、申請方法など順を追って詳しく説明しますので、自社に合った活用方法をぜひ見つけてください。
2.助成金の4つのコースと目的の違い
「働き方改革推進支援助成金」は、中小企業が抱えるさまざまな課題やニーズに合わせて、取り組みやすいように4つのコースに分類されています。それぞれのコースには明確な目的や対象となる企業が設定されているため、自社に適したコースを選ぶことが、助成金の活用を成功させるための重要なポイントとなります。
以下では、この4つのコースの違いとそれぞれの目的について、初心者にもわかりやすく解説します。
① 業種別課題対応コース
業種別課題対応コースは、建設業、運送業、医療機関(病院等)、情報通信業、宿泊業など、特定の業種を対象としたコースです。
これらの業種は、特に労働時間が長くなりやすく、働き方改革を進める上で固有の課題を抱えています。2024年4月から適用が開始された「時間外労働の上限規制」に対応するため、長時間労働の削減や週休二日制の導入など、業界特有の課題を解決する取り組みが支援されます。
具体的には、以下のような取り組みが対象になります。
- 業務効率化に資する設備の導入(例:建設業の建機導入、運送業のデジタコ導入)
- 業務プロセス改善のための専門家によるコンサルティング
- 従業員の労働時間短縮や週休二日制の促進に向けた研修の実施
業種別の特殊事情に応じた取り組みに対して、支給額の上限が比較的高く設定されているため、対象業種の企業は特に積極的に活用を検討すべきコースです。
② 労働時間短縮・年休促進支援コース
こちらは、すべての業種の中小企業が利用可能な、最も基本的なコースです。主に、以下の2つの目標を達成するための取り組みを支援します。
- 時間外労働の削減(残業時間を減らすための取り組み)
- 年次有給休暇や特別休暇の取得促進
例えば、勤務管理システムの導入や、労働時間管理のルール整備、社内研修の実施といった取り組みが対象となります。
中小企業の多くが抱える「残業時間の多さ」や「有給休暇の取得率の低さ」といった一般的な課題に対応するため、利用しやすい制度になっています。基本的な働き方改革を進めたい企業にとって、最も利用しやすいコースといえるでしょう。
③ 勤務間インターバル導入コース
このコースは、勤務終了後から次の勤務開始までの間に一定の休息時間(勤務間インターバル)を確保する制度を導入することを目的としています。
勤務間インターバル制度は、労働者が十分な休息を取り、健康を保ちながら働けるようにすることを狙いとしています。この制度を新たに導入、あるいは拡充するために必要な取り組みや設備投資が助成の対象となります。
具体的な対象となる取り組みの例としては、
- 勤務管理システムや勤怠管理システムの導入
- インターバル制度導入に関する従業員や管理職向けの研修の実施
などがあります。
働き手の健康管理やワークライフバランスの向上を重視している企業に適したコースといえるでしょう。
④ 団体推進コース
団体推進コースは、中小企業の業界団体(商工会、事業協同組合など)が主導して、複数の傘下企業の働き方改革をまとめて支援することを目的としています。
団体が中心となって傘下企業全体の労働条件改善を図り、労働時間短縮や賃金引き上げ、職場環境改善のための設備導入や研修、コンサルティングを実施する際に助成が受けられます。
団体推進コースの大きな特徴は、助成率が100%(全額)である点です。また、他のコースに比べて助成金の支給上限が高く設定されており、広域(複数の地域や都道府県)にまたがる団体の場合は最大1,000万円の助成が可能です。
複数の企業を一括して支援するため、業界全体の課題解決を図りたい企業団体に特におすすめのコースです。
3.支給対象となる取り組みと対象経費
働き方改革推進支援助成金を受けるためには、「国が認める特定の取り組み」を行う必要があります。また、助成される経費は、この認められた取り組みに直接かかった費用に限られています。この章では、具体的にどのような取り組みや経費が助成の対象となるのかをわかりやすく説明します。
支給対象となる具体的な取り組み例
助成金の対象となる主な取り組みは、以下のような内容です。
① 労務管理担当者への研修実施
人事・総務担当者など労務管理に関わる担当者を対象に、労働時間短縮や有給休暇取得促進など、働き方改革に関する研修を実施することが対象となります。研修の費用(講師への謝金、会場費用など)が対象経費です。
② 従業員向けの研修や周知・啓発活動
従業員に向けて、働き方改革の重要性を伝えるための研修会や説明会、社内での周知活動にかかった費用(教材費用、講師費用、資料作成費用)が助成対象となります。
③ 専門家によるコンサルティングの利用
社会保険労務士、中小企業診断士などの外部専門家に、働き方改革のための制度設計や課題解決のためのコンサルティングを依頼した際の費用が対象経費となります。
④ 就業規則や労使協定などの作成・変更
長時間労働の削減や有給休暇促進のために、就業規則や労使協定を新たに作成したり、変更するために専門家に相談した場合、その費用が助成対象です。
⑤ 人材確保に向けた取り組み
働きやすい職場づくりを進めるために、新たな人材を確保するための採用活動(広告費用や求人票作成費用)にかかる費用も対象となります。
⑥ 労務管理用のソフトウェア・機器の導入
勤怠管理システムやタイムレコーダーなど、労働時間の把握や休暇取得状況を管理するための機器やソフトウェア導入にかかる費用が対象経費となります。
⑦ 業務効率化につながる設備や機器の導入
特に業種別課題対応コースでは、業務効率化によって労働時間短縮が見込める機器・設備の導入が広く認められています。たとえば、小売業のPOSシステム、建設業の建設機械、運送業のデジタルタコグラフなどが対象です。
対象経費として認められるもの・認められないものの例
助成金の対象経費には、以下のようなものがあります。
- 外部専門家への謝礼やコンサルティング料
- 社員研修費用(講師謝金、教材作成費、会場費など)
- システムやソフトウェアの購入費用やリース費用
- 就業規則などの作成にかかる行政書士や社労士への支払い費用
- 勤怠管理機器や労務管理設備の購入費用
一方で、以下のような経費は原則として対象外となりますので注意が必要です。
- パソコン、タブレット、スマートフォンなど、一般的で汎用性の高い機器の購入費用
- 企業の通常業務で日常的に使用される消耗品(事務用品や消耗品類)
- 自社従業員に対する給与や人件費
- 一般的なオフィス家具や設備(机、椅子、ロッカー等)
助成の対象となる経費は「働き方改革の取り組みに直接必要な費用」であることが基本的な考え方となります。
助成金活用のポイントと注意点
支給対象となる取り組みを行う際に、特に以下のポイントに注意しましょう。
- 必ず助成金の申請前に計画を作成し、承認(交付決定)を受けることが必要です。
事後の申請は認められないため、事前の計画立案と交付申請が非常に重要です。 - 対象経費の証明書類(領収書・請求書等)をきちんと保管し、支払記録を明確にしておく必要があります。助成金の支給申請時に必ず提出が必要になります。
- 支給対象外の経費を含めないよう注意が必要です。
誤って支給対象外の経費を申請すると、助成金が認められない、または減額されることがあります。
働き方改革推進支援助成金を最大限活用するには、自社の取り組みが本当に対象になるかを事前にきちんと確認することが重要です。厚生労働省の公式資料や、必要に応じて社会保険労務士など専門家に相談しながら、適切な計画を立てましょう。
4.助成金の支給額と補助率の違い
「働き方改革推進支援助成金」は、行う取り組みの内容や規模、達成した成果に応じて、助成金の支給額や補助率が異なります。この章では、各コースの具体的な支給額の目安と補助率について、初心者にもわかりやすくまとめて解説します。
助成率(補助率)とは?
まず、「助成率(補助率)」とは、取り組みのために企業が支払った費用(対象経費)のうち、国から助成される割合のことです。
例えば、助成率が75%(4分の3)の場合、企業が100万円を費やしたとき、国から75万円が助成され、実質の企業負担は25万円で済むことになります。
この助成率は企業規模や選択したコースによって異なり、原則として次のようなルールになっています。
- 一般的な中小企業:75%(対象経費の4分の3)
- 特に規模が小さい企業(従業員30人以下):80%(対象経費の5分の4)
- 団体推進コースを利用する企業団体:100%(対象経費の全額)
次に、各コースの助成金支給額(上限額)と補助率を具体的に見ていきましょう。
コース別の支給上限額と補助率
① 業種別課題対応コース
- 補助率:75%(従業員30人以下の小規模企業は80%)
- 支給額上限:最大250万円程度
特定の業種が長時間労働の削減や休日取得促進などの課題解決に取り組む場合、達成した成果に応じて助成金が支給されます。特に、時間外労働の削減目標や週休二日制の導入目標を最大限達成した場合に、上限額が高く設定されます。
具体的な目安としては、取り組み内容や達成度に応じて150万円から250万円の範囲で支給されることが一般的です。
② 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 補助率:75%(従業員30人以下の小規模企業は80%)
- 支給額上限:最大200万円程度(基本の成果目標で150万円、有給取得促進などの追加目標で上限加算あり)
時間外労働の削減目標や、有給休暇の取得促進目標の達成度合いに応じて、支給額が決まります。例えば、月の残業時間を60時間以下に設定・達成した場合には上限150万円、さらに有給取得率の向上などを達成した場合には最大で200万円程度まで増額されます。
一般的な中小企業が取り組みやすく、最も基本的なコースのため、多くの企業に活用されています。
③ 勤務間インターバル導入コース
- 補助率:75%(従業員30人以下の小規模企業は80%)
- 支給額上限:最大120万円程度
勤務終了から次の勤務開始まで一定の休息時間(インターバル)を設ける取り組みを新たに導入・拡充した場合、その取り組み内容に応じて助成されます。休息時間が9時間以上の場合は上限120万円、短い休息時間(例:7時間以上)の場合は上限が少し低くなる仕組みです。
労働者の健康やワークライフバランス改善のために制度を新規導入する企業に最適なコースです。
④ 団体推進コース(企業団体向け)
- 補助率:100%(経費の全額を助成)
- 支給額上限:通常500万円(広域団体は最大1,000万円まで引き上げ可能)
団体推進コースは、商工会や業界団体など、複数の中小企業をまとめて支援するためのコースです。対象経費が全額(100%)助成されるため、団体にとって大変メリットの大きい制度です。通常、助成上限は500万円ですが、複数の都道府県や市町村にまたがる広域的な団体の場合は、最大1,000万円まで助成金額が引き上げられます。
団体として働き方改革を推進し、多くの傘下企業を支援する際に最適なコースです。
助成額が増える「賃上げ加算」について
各コースとも、働き方改革の取り組みに加えて、従業員の賃金引き上げを実施すると、支給額がさらに加算される場合があります(賃上げ加算制度)。具体的には、従業員の賃金を一定以上引き上げた場合、追加で助成金が上乗せされる仕組みです。
賃上げを伴う取り組みの場合、助成金の支給額を最大限まで引き上げられる可能性がありますので、活用を検討している企業は、事前にこの制度についても確認するとよいでしょう。
助成金を受け取るためには、目標とする成果を達成することが条件となります。計画した目標を達成できない場合は、助成金が支給されない、または減額されることもあります。
そのため、計画段階から無理のない達成可能な目標を設定し、実施中もしっかりと進捗管理をすることが非常に重要です。支給額と補助率の違いを理解し、自社に適したコースを選択して、助成金を最大限に活用しましょう。
助成金申請の流れと手続き
働き方改革推進支援助成金を受け取るためには、あらかじめ決められた申請手続きを正しく行う必要があります。申請手続きは難しそうに感じられるかもしれませんが、段階を追って進めれば初心者でも問題なく行えます。この章では、助成金の申請から支給までの流れをわかりやすく順を追って説明します。
① 事前準備と計画策定
助成金の申請は、実際に取り組みを始める前の計画段階からスタートします。まずは次のことを行います。
- 助成金の対象となる取り組みを明確にする
自社の課題や目標を整理し、助成対象となる取り組みを選びます。
対象となる経費をリストアップし、予算の目安を立てます。 - 申請書類の準備
交付申請書(計画書)の作成が必要です。計画書には取り組みの内容、達成目標、費用見積もり、導入機器・設備の仕様などを具体的に記載します。
見積書やカタログなど、取り組みに必要な資料も事前に準備しましょう。
助成対象経費は、交付決定日以降に発注・支払いしたものに限られます。そのため、交付決定を受ける前に取り組みを始めてしまうと対象外になってしまいますので注意してください。
② 交付申請の提出
計画書など必要書類を準備したら、「交付申請」を行います。
- 申請先は「都道府県労働局」
自社の所在地を管轄する労働局の「雇用環境・均等部(室)」に申請書類を提出します。
(持参・郵送・オンライン申請(jGrants)などが可能です。) - 申請期間
例年、年度初め(4月)から11月下旬ごろまでが一般的です。ただし、予算に限りがあるため早めに申請するのが望ましいでしょう。 - 申請に必要な書類例
交付申請書(事業実施計画書を含む)
取り組みに関する見積書(導入する機器やシステムなど)
会社概要や組織図など、労働局が求める追加資料
③ 交付決定と取り組みの実施
申請書類を提出した後、労働局で審査が行われ、問題がなければ「交付決定通知書」が届きます。
- 交付決定通知が届いたら取り組みを開始
通知書に記載された日付以降に、計画した取り組みを実施します。
計画書に沿って、機器の導入や研修、コンサルティングなどを進めます。 - 経費支払いの注意点
経費の支払いは必ず銀行振込など、支払いの記録が残る方法で行います。現金払いは基本的に認められません。
クレジットカードで支払う場合、引き落としが「支給申請日までに完了していること」が条件となります。
④ 支給申請の提出
取り組みが完了したら、実績に基づき助成金を受け取るための「支給申請」を行います。
- 支給申請に必要な書類例
支給申請書(実施結果報告書を含む)
経費の支払いを証明する書類(領収書、銀行振込控えなど)
取り組みの達成状況を確認できる書類(就業規則、労使協定の写し、勤務実績表など) - 申請時の成果目標達成の確認
当初計画した目標(例:残業時間の削減、有給取得促進、インターバル制度導入など)が達成されていることが求められます。
未達成の場合、助成金が支給されない、あるいは減額される可能性がありますので注意しましょう。
⑤ 助成金の支給(受給)
支給申請が労働局で審査され、問題なく認められると「支給決定通知書」が送付されます。
- 助成金の振込
通知後、指定した口座に助成金が振り込まれます。
振込まれたことを確認したら、助成金の手続きは完了です。
申請手続きの注意点とポイント
スムーズに助成金を受け取るためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 計画は必ず事前に作成し、交付決定後に取り組みを開始すること
交付決定前に開始した取り組みは対象外になるため注意が必要です。 - 経費の管理は厳密に行い、支払いの記録を必ず保管しておくこと
書類不備があると支給申請時に問題になりますので、領収書や銀行記録を正確に管理しましょう。 - 成果目標は達成可能な範囲で設定すること
達成が難しい目標を設定すると助成金が受けられないこともあるため、現実的な目標を定めましょう。
働き方改革推進支援助成金の申請は手順をしっかり守れば難しくありません。初めての方でも本章を参考に計画的に進めれば安心して手続きが行えます。制度を活用して、ぜひ働きやすい職場環境づくりに役立ててください。
まとめ:働き方改革推進支援助成金を活用して、職場環境の改善を!
「働き方改革推進支援助成金」は、中小企業が抱える「労働時間の削減」「有給休暇の取得促進」「従業員の健康管理」といった課題を解決するために必要な費用を、国が大幅にサポートする制度です。
特に、中小企業の社長にとっては、働き方改革にかかるコストやノウハウ不足が大きな課題になることが多いでしょう。この助成金制度を活用することで、経費の負担を軽減しながら職場の環境改善を進め、従業員が安心して働ける環境を整えることが可能になります。