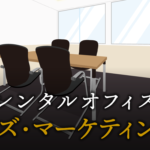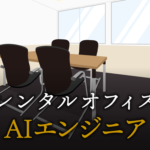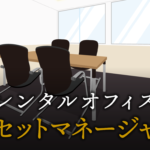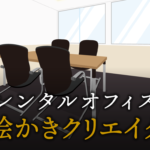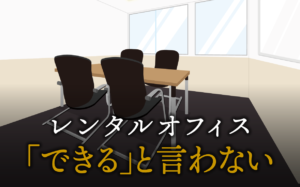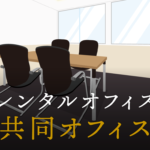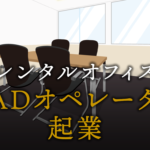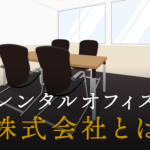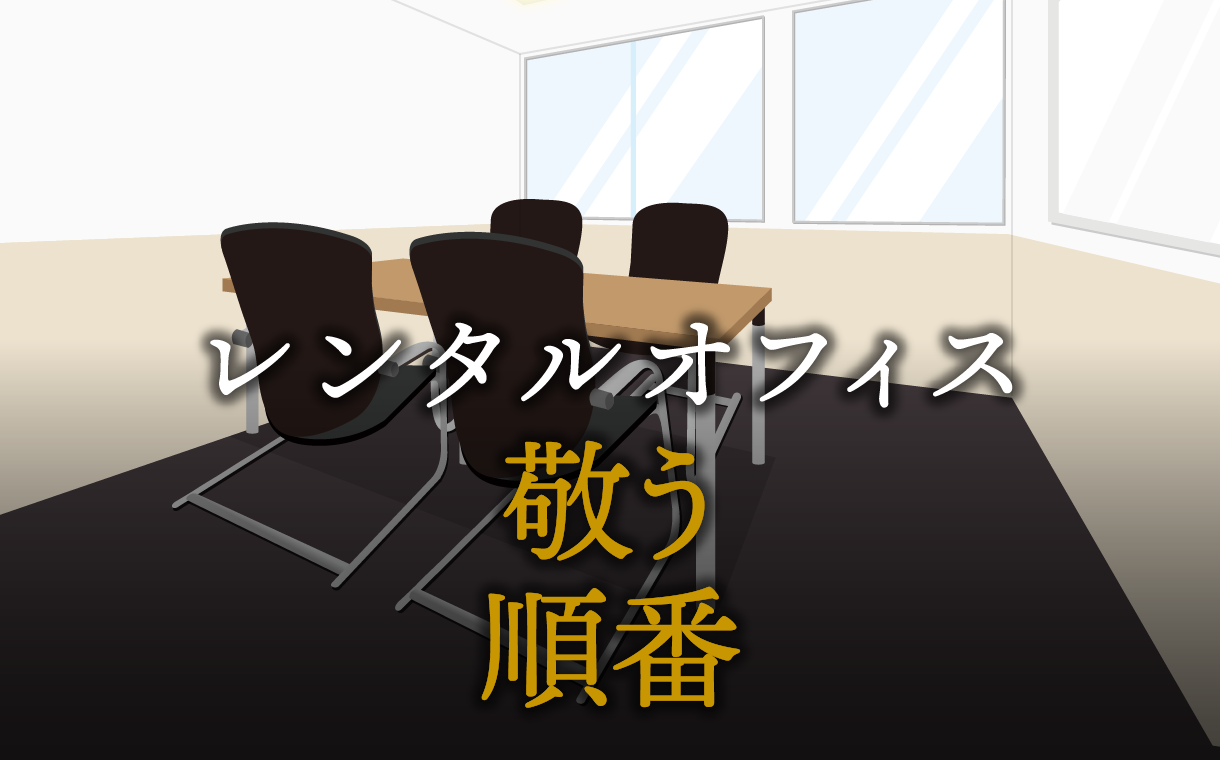
日本の会社では、役職や年次、社内の慣習などによって自然と序列が生まれます。一般的には、社長や役員が最上位に位置し、その下に部長、課長、係長と続きます。しかしながら、必ずしも役職だけで決まるわけではなく、勤続年数や社内での影響力、人間関係が影響することもあります。
実際のところ、日本の企業では具体的にどのような要素が上下関係を決めるのでしょうか?本記事では、会社における上下関係について詳しくお伝えします。
目次
会社の上下関係は役職 > 年齢 > 入社時期が一般的
会社の上下関係については、これといった正解はありませんが、一般的には役職 > 年齢 > 入社時期の順番で敬うのが正しいと言われています。ただし、会社によっては年齢と入社時期が逆になることもあるようです。
役職
一番重要なのはやはり「役職」となりますが、通常の会社の場合には次のような順番で役職の序列は決まってきます。
- 会長(相談役・顧問)
- 社長(代表取締役)
- 副社長/専務取締役/常務取締役
- 本部長・事業部長など
- 部長
- 次長
- 課長
- 係長
- 主任
- 一般社員
当然ながら、自社に存在しない役職もあるかもしれませんが、このような序列を意識して敬意を払えば、大きな問題にはならないと考えられます。
年齢
次の優先順位としては「年齢」があります。役職が同じ場合には、年齢が上の人が目上と見なされることが多いため、席次などを考慮する場合には気を付けましょう。
入社時期
入社時期は年齢と比べた場合、上下関係の下に位置するとされています。ただし、特定の条件下では入社時期が早い人が役職の上の人より影響力を持つことがあります。
年功序列の文化が強い企業の場合、役職が同じでも勤続年数が長い人が上とされることがあり、役職が下でも年次が上の人が「先輩」として敬意を払われることがある点には注意しなければなりません。
たとえば、後輩の「部長」と先輩の「係長」がいた場合、公式な序列は部長が上ですが、係長が長年の経験を持ち社内の影響力が大きいことがあり得ます。ですから、該当する人物の性格などを考慮して接していかないとトラブルに発展する可能性がありますので、十分気を付けましょう。
役職・年齢・入社時期以外の影響要素
役職や年齢、入社時期以外にも上下関係を決定づける要素は存在します。
たとえば、職務の重要度などはその例です。役職がなくても、技術専門職やプロジェクトリーダーなどとなった人の発言権が強い場合もあり、場合によっては役職や年齢を凌駕するケースもあり得ます。
また、社内の影響力も上下関係に影響を及ぼす要因のひとつ。たとえば、社長の親族であったり、縁故採用などの場合には、役職や年齢関係なしに社内での立場を敬わないといけない状況が考えられます。
上下関係を円滑にする方法
会社内での上下関係を円滑にするためには、次のような方法を実践するのがよいでしょう。
相手を尊重する
上下関係を円滑にするには、まずお互いの立場や役割を尊重し敬うことが大切です。上司や年齢が上の人、入社時期が古い人は、部下に対して指示を出すだけでなく、意見を聞き、適切なフィードバックをすることで信頼関係を築くことができます。一方で、部下や年齢が低い人、入社時期が新しい人は、上司の考えを理解し、報告・連絡・相談を適切に行うことで、円滑なコミュニケーションを心掛けることが必要です。
相手に合わせた言葉遣いや振る舞いを実践する
相手の立場を考えた言葉遣いや態度も関係を良好に保つポイントです。上司や年齢が上の人、入社時期が古い人は権威的になりすぎず、部下や年齢が低い人、入社時期が新しい人が意見を言いやすい雰囲気を作ることが求められます。逆に、部下や年齢が低い人、入社時期が新しい人は礼儀を忘れず、適度な敬意を示しながらも、必要な意見をしっかり伝えることが大切です。
日ごろからコミュニケーションを密に取る
日頃からコミュニケーションをとることも、上下関係をスムーズにするための鍵となります。仕事上の話だけでなく適度な雑談を交えることで、お互いの人となりを理解しやすくなり、関係がより円滑になります。特に日本の職場では、仕事の場以外でも信頼関係を築くことが大切とされるため、食事会や社内イベントを活用するのも有効です。
相手のモチベーションを高める行動をとる
さらに、相手に対して感謝の気持ちを伝えることも忘れてはいけません。努力を認め、ねぎらいの言葉をかけることで、相手側のモチベーションは高まります。そうすることを積み重ねていけば、良好な関係を維持しやすくなります。
上下関係を円滑にするためには、お互いが歩み寄り、信頼とコミュニケーションを積み重ねることが不可欠です。
上下関係を重視する企業は時代遅れなのか?
昨今実力主義を掲げる企業が増えてきている中、上下関係を重視している企業が必ずしも時代遅れとは言えず、上下関係のあり方次第で組織の良し悪しが決定していくと考えられています。
上下関係が必要だと考えられる理由
上下関係が必要な理由として、上下関係があることにより組織の秩序や効率性を保つことが挙げられます。明確な指示系統があると意思決定がスムーズになり、役割分担がはっきりするため、組織全体がうまく機能しやすくなります。特に日本のような伝統的な企業文化を重んじる場合には、経験や年功を重視することで、安定した組織運営を実現できます。
しかし、単なる上下関係の強調が「時代遅れ」と考えられるのは、権威主義的な文化が残りすぎているケースです。たとえば、「年次が上の人の意見が絶対」「役職があるだけで発言権が強い」「部下が意見を言いにくい環境」といった、柔軟性のないヒエラルキーは、現代のビジネス環境においてはデメリットになりがちです。その結果、意思決定が遅れたり、若手や新しいアイデアが活かされない状況を生み、結果として競争力が落ちる原因になります。
今後、フラットな組織体制を導入する企業は増えていく
最近では、フラットな組織や精神的な安全を重視する企業が増えてきており、年齢や役職に関係なく意見を出し合う環境が求められています。つまり、上下関係よりも「成果」や「専門性」を重視し、オープンなコミュニケーションを大切にすることで、より効率的で創造的な働き方を実現している企業が続々と誕生しているのです。
ただし、伝統的な上下関係が悪いというわけではありません。あくまで「形だけの上下関係」になってしまっている場合が問題です。ですから、上下関係を活かしながらも実力や意見を尊重する文化を持つ企業であれば、今後も競争力を保ち続けることでしょう。
まとめ
会社における上下関係は、役職 > 年齢 > 入社時期で敬うのが一般的だと言われていますが、成果主義の現在では、必ずしもこのような順番で上下関係が決まるというわけではありません。
最近では、若い世代を中心にフラットな組織が好まれる傾向がありますが、それでも上下関係を重視する企業は依然として多いのが現状です。上下関係が円滑な組織を築くためには、相手を思いやる心を持つ、コミュニケーションを欠かさず取るなど基本的な行動を忘れないことが重要となる点は、しっかりと覚えておきましょう。