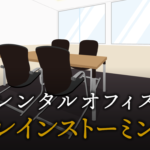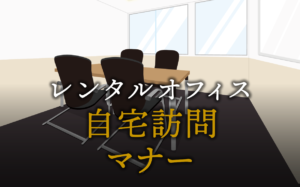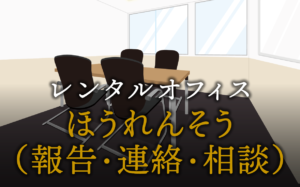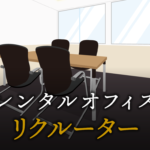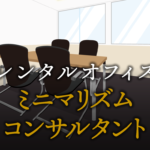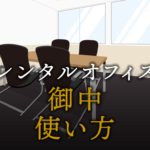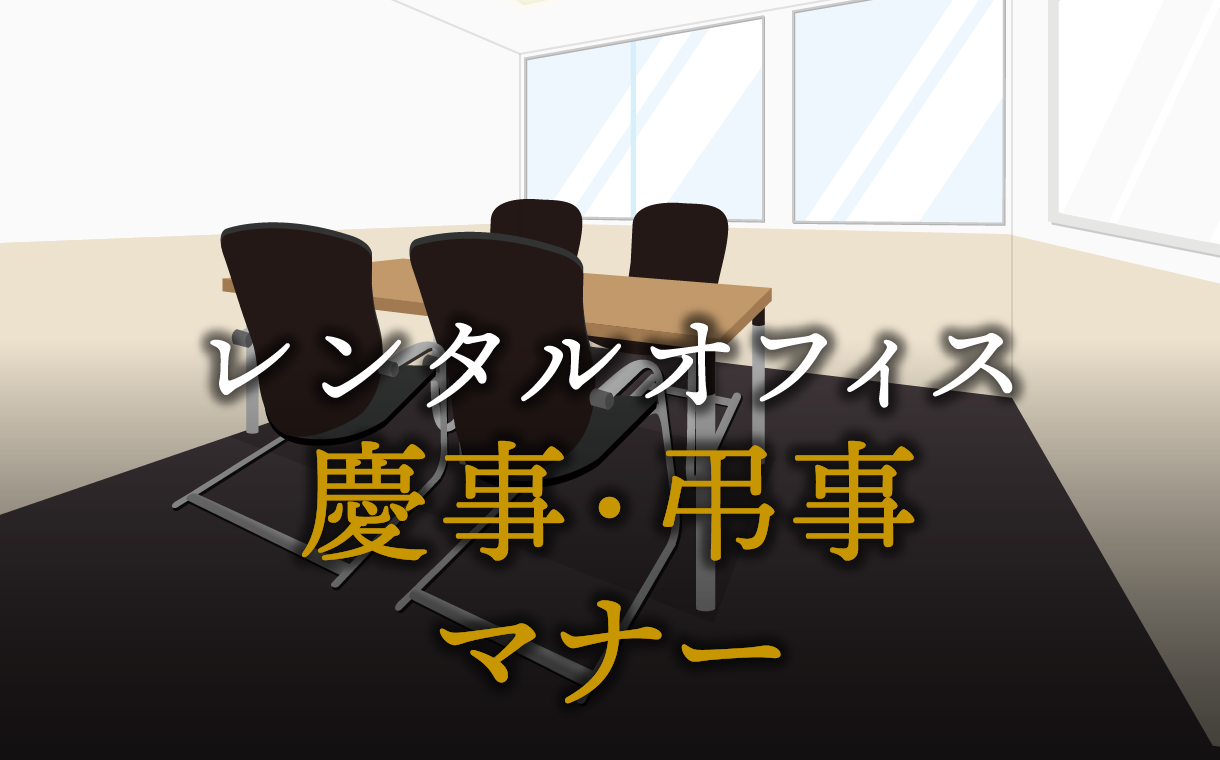
年齢を重ねるにつれ、慶事や弔事といった儀式や行事への参加は増えていきます。若い世代であまり慶事も弔事への参加の経験がない方の場合には、どのような振る舞いをしたらいいかよくわからないまま、なんとなく参加してしまったという人も多いと思います。慶事も弔事も似たようなものと思いがちですが、正反対の儀式・行事となるため、適用するルールもそれぞれ異なります。
今回は慶事・弔事への参列マナーについてお伝えしていきます。
目次
慶事とは?
「慶事」とは、喜ばしい出来事やお祝いごとのことを指します。特に結婚や出産、長寿のお祝い、進学、昇進など、人生の中で特に祝うべき幸せな出来事が慶事には含まれます。日本では、慶事には贈り物やお祝いのメッセージを送る習慣があり、祝いごとに関連する儀式や行事も行われることが多いです。
弔辞とは?
「弔事」とは、故人を悼み、哀悼の意を示すための儀式や行事のことを指します。一般的には、葬儀や告別式、法事などが弔事に該当します。このような場では、故人への別れを告げ遺族を慰めることが目的となり、慶事とは正反対なものとなります。
なお、弔事は宗教的な儀式が含まれる場合もあり、故人の信仰や文化に基づいて異なる形式で行われるのが基本です。
慶事の種類
慶事の種類ですが、「結婚関連」「誕生・成長関連」「長寿関連」「学校関連」「仕事関連」「その他」といったジャンルにわかれます。具体的には次のような儀式・行事が挙げられます。
結婚に関する慶事
- 婚約:結婚の約束を公表する行事
- 結婚式:新郎新婦の結婚を祝う儀式や披露宴の場
- 結婚記念日:結婚した日を記念してお祝いする。銀婚式(25年目)や金婚式(50年目)は節目として特に重要視される
誕生や成長に関する慶事
- 出産:子どもの誕生をお祝いする
- お宮参り:生後1ヶ月頃に神社に参拝し、子どもの健やかな成長を願う行事
- 七五三:3歳、5歳、7歳の子どもの成長を祝う日本の伝統的な行事
- 成人式:20歳を祝う儀式。日本では市区町村が主催することが多い。18歳に成人年齢が引き下げられたが、成人式は20歳に行う自治体がほとんど
長寿を祝う慶事
- 還暦(60歳):干支が一巡する60歳をお祝いする。赤いちゃんちゃんこを着る
- 古稀(70歳):70歳の長寿をお祝いする。杜甫の詩「人生七十古来稀なり」から
- 喜寿(77歳):77歳をお祝いする。喜の草書体「㐂」が「七十七」と読めることから
- 傘寿(80歳):80歳をお祝いする。傘の略字が八と十を重ねたものに見えることから
- 米寿(88歳):88歳をお祝いする。米の字を崩して書くと八十八と読めることから
- 卒寿(90歳):90歳をお祝いする。卒の略字が九と十を重ねたものに見えることから
- 白寿(99歳):99歳の祝い。百から一の部分を除くと白の文字になることから
- 百寿(100歳):100歳をお祝いする
学校に関する慶事
- 入学式:学校に入学することを祝う式典
- 卒業式:学校の課程を修了したことを祝う式典
仕事に関する慶事
- 就職祝い:就職決定をお祝いする
- 昇進・昇格:仕事で昇進や昇格を果たしたことお祝いする
その他の慶事
- 新築祝い:新しい家を建てたり購入した際にお祝いする
- 引っ越し祝い:新しい住居に引っ越した際にお祝いする
- 開業/開店祝い:新しい事業や店舗を始めた際にお祝いする
慶事のマナー
慶事において次のようなことはマナーとしてぜひ知っておきたいものです。
のし・水引について
慶事のマナーとして多くの方が悩むのが「お祝い」の包み方、書き方ではないでしょうか?慶事のお祝いは、基本的に「のし紙」を付けてお渡しするのがマナーです(印刷でもOK)。その際に間違った「のし」や「水引」を選んでしまうと意味が異なってしまい、相手を不快にさせる場合がありますので注意しましょう。
- 結婚式の場合:紅白、金銀、または赤金の10本結び切り
※結びきりにするのは結婚を何度もしないように(一度きりにするため) - 出産や成長、長寿、昇進など:紅白の5本蝶結び
慶事に包む金額について
慶事の内容によって金額相場は異なりますが、慶事の際には1万円・3万円・5万円など、奇数の金額を包むのが一般的です(結婚式の場合には3万円が基本)。偶数や「4・6・9」といった数字になるような金額を包むのは控えましょう。
慶事に参加する際の服装について
慶事の服装については、フォーマルウェアを着用するのがマナーです。
たとえば結婚式の場合、男性は黒やネイビー、グレーなどのフォーマルなスーツが基本となります。なお、ワイシャツは白にしておくのが一般的です。女性の場合は、ドレスやワンピースを着ることが多いものの、あまり派手すぎないようにします。
弔事の種類
弔事の種類は「葬儀関連」「法事関連」「その他」に分けられます。具体的には次のような儀式・行事が挙げられます。
葬儀関連
- 通夜:葬儀の前夜に行われる儀式で、故人と最後の夜を共に過ごし、夜通し故人を見守る伝統がある
- 葬儀:故人を弔って亡くなった方に別れを告げる正式な儀式。宗教的な儀式が含まれることが多く、家族や友人が参列するもの
- 告別式:葬儀の一部として行われ故人と最後の別れをする場のこと。友人や知人、職場関係者が参列することがほとんど
- 火葬式:故人の遺体を火葬する儀式。葬儀の一部として行われる
- 納骨式:故人の遺骨をお墓に納める儀式で、一般的には四十九日法要の後に行われる
法事関連
- 初七日法要:故人が亡くなってから7日目に行われる供養で、家族や親しい友人が集まって故人の冥福を祈る
- 四十九日法要:故人が亡くなってから49日目に行われる供養であり、仏教ではこの日をもって故人の魂が成仏する日とされている
- 年回忌法要:一周忌、三回忌、七回忌など、故人が亡くなってから1年目、3年目、7年目に行われる追善供養でこれ以降も13回忌、33回忌などの節目に法要が行われる
その他の弔事
- 弔電:遠方や出席できない場合に、故人や遺族に対して哀悼の意を示す電報のこと
- 墓参り:故人の墓を訪れ、花を供えたりお祈りをする行事。通常はお盆やお彼岸、命日などに行われる
弔事のマナー
慶事同様、弔事においてもマナーが存在します。恥をかかないように、経験を通じながらも覚えていきましょう。
のし・水引について
弔事における香典や供え物には、基本的にのしは付けずに水引をかけたものをお渡しします(印刷でもOK)。
- 通夜・葬儀の場合:黒白または双銀の5本結び切り
- 香典返し:黒白の5本結び切り
弔事に包む香典について
弔事の際には香典を包んで持参しますが、香典の相場については亡くなった故人との関係性により、包む金額が異なります。
- 同僚や同じ部署の社員が亡くなった場合:3,000円〜5,000円
- 上司や部下が亡くなった場合:5,000円〜10,000円
- 取引先や顧客が亡くなった場合:5,000円〜10,000円
- 会社の上層部や役員が亡くなった場合:10,000円〜30,000円
弔事に参加する際の服装について
慶事の服装については黒のフォーマルスーツが基本です。シャツは白、ネクタイと靴下、靴は黒で統一します。女性の場合は黒のワンピースやアンサンブルスーツが基本となりますが、あまり露出が多くないものにしましょう。なお、過度なアクセサリーは避けるようにしましょう。