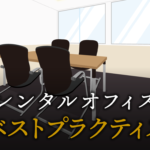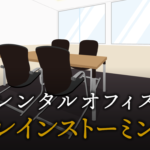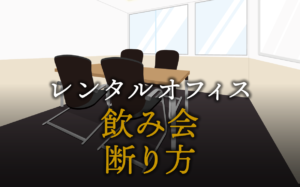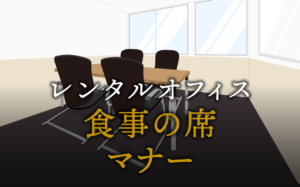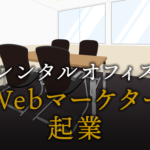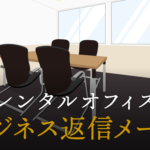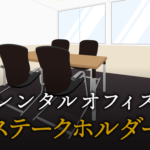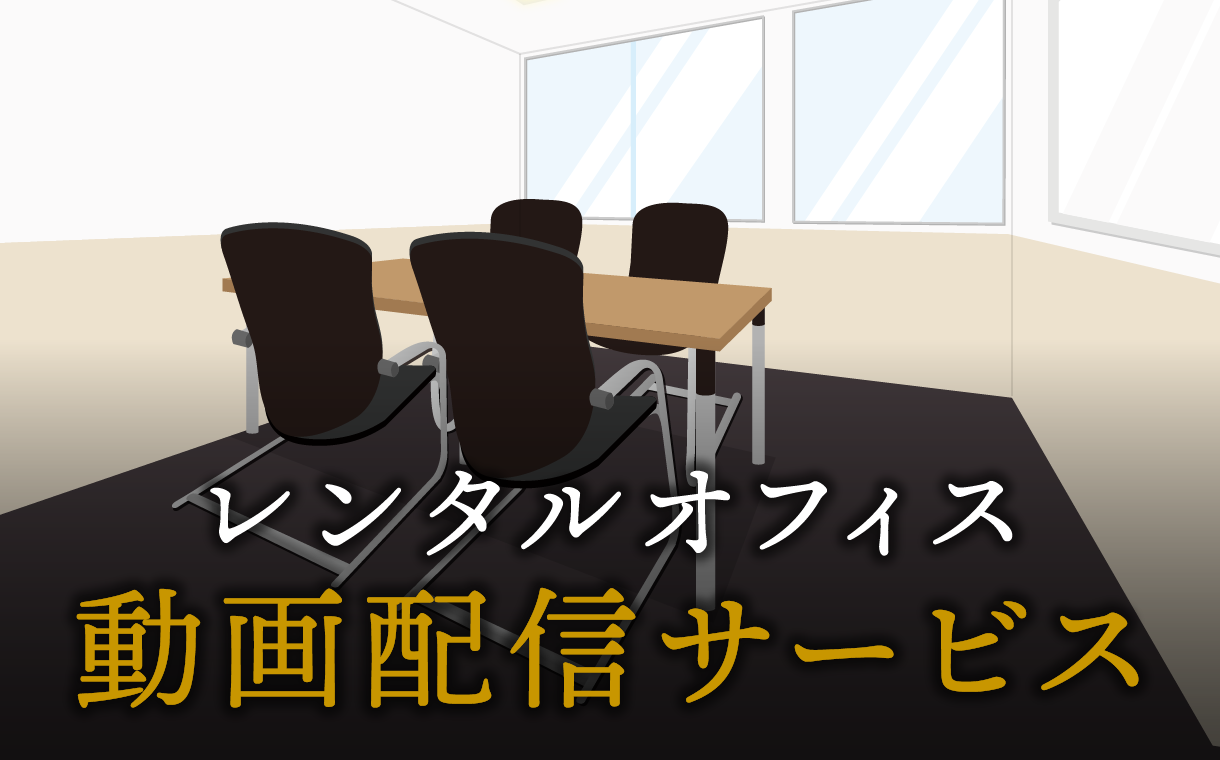
YouTubeをはじめとした動画配信が一般的となった今、動画配信サービス(VOD)は人々の生活になくてはならないものになってきています。
このように動画配信サービスを利用する人がいる一方で、動画配信を仕事として行っている企業や団体、個人の方もいるわけで、中には動画配信サービスを事業としてスタートさせるべく起業を目指す人もいるのではないでしょうか。
今回は動画配信サービスで起業する方法について見ていきたいと思います。
目次
動画配信サービスとは?
動画配信サービスとは、ネットを通じて映画やドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、ライブ配信などの映像コンテンツを視聴者に提供するサービスのことを言います。
ユーザーは、スマートフォンやタブレット、パソコン、スマートテレビなどのデバイスを使用し、場所や時間を問わずにコンテンツを楽しむことができるのが特徴です。
動画配信サービスの利用方法としては、月額定額料金を支払うサブスクリプション方式や、作品ごとに料金を支払うレンタル方式などさまざまな料金体系が展開されています。
代表的なサービスには、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなどがあり世界中にも多くの利用者がいます。
この動画配信サービスは、テレビやDVDに代わる形で急速に普及しており、特に若い世代に人気があります。
利用者は視聴するコンテンツを自分で選択でき、視聴開始から終了までの自由度が高いことが特徴です。
企業向けの動画配信サービス
企業向けの動画配信サービスとは、主にビジネスや企業活動において、社員やビジネスの利害関係者に向けた動画コンテンツを提供・共有するためのプラットフォームやシステムです。
たとえば、従業員のトレーニングや社内コミュニケーション、マーケティング、製品発表、ウェビナー、セミナーなど、幅広い用途に利用されます。
このような企業向けの動画配信サービスの特徴ですが、社内トレーニングや教育に役立つ点が最も大きいメリットです。
オンデマンドで研修動画や教育コンテンツを提供することで、場所や時間に関係なく自分のペースで学習できるようになりますので、効率的な教育機会の提供および新入社員の育成が可能になります。
また紙の印刷が不要となるので事務コストが削減できます。
また、動画を使った会議やプレゼンテーション、重要な社内発表をオンライン配信することを可能にし、複数拠点のある企業であれば遠隔地にいる従業員やチーム間のコミュニケーションを強化したりすることができます。
特に、ライブ配信機能を使えば、リアルタイムでの情報共有やフィードバックが可能です。
これまで、本部での出張が必須であった会議もすべてオンラインで片付けられます。
ほかにも、外部向けのマーケティング、顧客向けのサービスにも動画配信サービスは活用されています。
たとえば、動画配信サービスを利用した新製品・サービスの紹介、ブランドプロモーション、顧客サポートのためのチュートリアル動画などを制作・配信し、コアなターゲットに効果的にアプローチすることができます。
もちろん、このような動画配信サービス利用においては、ID・パスワードによる制御、セキュリティやプライバシー保護も重要な要素として存在します。
動画配信サービスには、アクセス制限やデータ保護機能などが搭載されているもののあり、特定の従業員やパートナーだけにアクセスを許可するなど、機密情報であっても安全に取り扱うことが可能です。
動画配信サービスで起業するためには?
先ほどで紹介したNetflix、Amazon Prime Video、Huluのような動画配信サービスを一から起業して提供するのはかなり至難の業です。
しかしながら、後述のような特定の企業やメンバーだけが見られるような企業が制作・提供するコンテンツ動画配信システムを構築し、サービスを展開することは現実的に可能と言えるでしょう。
エンジニアとしてプログラミングができる方であればシステム自体を構築することは可能です。
あとは、利用者に応じた想定トラフィックに耐えられるようなサーバを用意し、運営を行うことができればよいだけです。
動画配信サービス構築において必要な機能・あると便利な機能
起業して動画配信サービスを提供するためには、ユーザーの満足度を高めスムーズなコンテンツ視聴を提供するための機能搭載が求められます。
ストリーミング機能
基本的な機能として、視聴中に動画を途切れなく再生するための高品質なストリーミング技術が必要です。
ユーザーのネットワーク状況に応じて自動的に画質を調整する「アダプティブビットレート」などの技術が求められます。
コンテンツライブラリの管理
複数の動画を見ることのできる動画配信サービスであれば、数ある動画の中からユーザーが簡単にアクセスできるようにするためのカテゴリー分けや検索機能が大事になってきます。
タグ付け、フィルタリング、レコメンド機能などがそれに該当します。
マルチデバイス対応
今は「ビジネスで使用する場合はパソコンから」という時代ではありません。
スマートフォンやタブレット、スマートテレビなど、さまざまなデバイスで視聴可能なプラットフォームを提供することも動画配信サービスのプラットフォーマーには大事です。
クロスプラットフォーム対応により、ユーザーはいつでもどこでも視聴が可能となります。
顧客管理機能
視聴者のアカウント管理もさることながら、ユーザーマイページを用意し、これまで視聴した動画の履歴や、アクセス状況などがわかるような機能も必要です。
DRM(デジタル著作権管理)
掲載しているコンテンツの違法なコピーやダウウンロードを防ぐためには、セキュリティ機能やデジタル著作権管理(DRM)の導入が求められます。
これにより、コンテンツの配信元や権利者を保護します。
ライブ配信機能
会議やセミナーをリアルタイムで配信するライブストリーミング機能もあると便利な機能のひとつ。さらにチャットや投票機能を搭載すれば、相互インタラクティブな情報のやりとりも可能となります。
多言語対応
グローバル展開している企業では、日本語以外の言語対応として、字幕や音声の多言語対応があると便利です。
最近はさまざまなサービスで多言語対応が一般化していますが、正確性もさることながら機能が搭載されていることで、多少言葉の違和感があっても顧客満足度は高くなります。
動画配信サービスとしての収入
自社で動画配信サービスを構築すれば、利用するユーザーからの定期利用料、コンテンツ提供企業からはコンテンツ掲載料などを獲得することができるでしょう。
また動画配信サービス自体の構築ノウハウを用いてシステム販売すれば、数百~数千万円のシステム開発費用、数十~数百万の運用保守費用が得られる可能性もあります。
ただし、動画配信サービスを一から構築するのは非常に大変な労力がかかりますし、顧客がついていないスタートアップ時には資金が枯渇してしまうリスクも多大にあります。
とはいえ、一度運営が軌道に乗れば安定収入を得ることができやすいため、既存サービスとの連携等を図りながら同時のサービスを構築してみるとよいでしょう。
まとめ
YouTubeなどの動画コンテンツ制作でお金を稼ぎたいというスタートアップの起業家は多いと思いますが、ITスキルの高い人であれば動画配信サービスを運営する側のプラットフォーマーとして起業することも視野に入れていいかもしれません。
魅力あるコンテンツを掲載できる企業とのタイアップ、クローズド会員に向けて限定コンテンツを配信するためのシステム構築など、動画配信サービスを事業化しビジネスにつなげてみることに挑戦してみてはいかがですか?