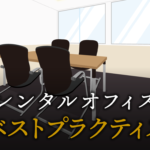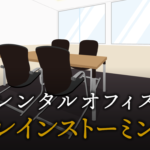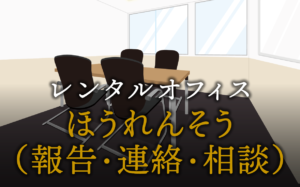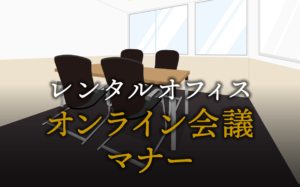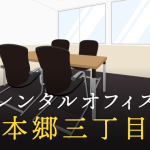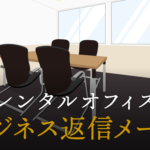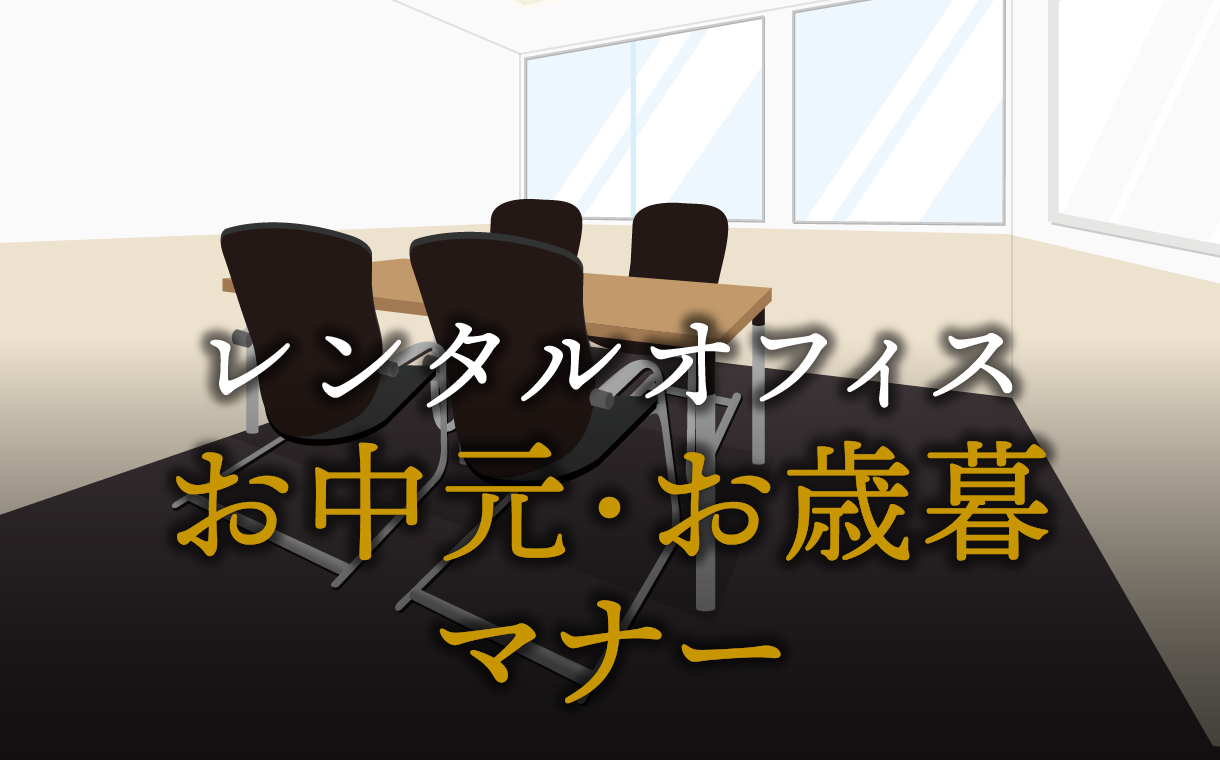
お中元やお歳暮は、昔に比べるとやり取りする機会は大きく減りましたが、それでも現在まで残る風習のひとつ。ビジネスにおいてはお世話になったお客様へ感謝の気持ちを表す贈り物として活用されています。
過去には、お中元やお歳暮の季節に、直接企業に出向いて渡していたこともありますが、最近は店舗やネットで簡単に注文するなど、形だけ贈っているケースも多いように感じます。
そんなお中元やお歳暮には贈る際のマナーがあることはご存じでしょうか?
本記事では、お中元やお歳暮のマナーについてお伝えしていきます。
目次
お中元とは?
まずはお中元について見ていきましょう。お中元とは日本の伝統的な習慣のひとつで、主に夏にお世話になっている方や親しい方に感謝の気持ちを込めて贈り物をする行事です。特にビジネスにおいては職場の上司や取引先などに贈ることが一般的となっています。お中元として贈るものとしては、日常的に使用できる食べ物や飲み物、季節の品(水ようかんやゼリー)などが多く選ばれます。
お中元を贈る期間は地域によっても多少異なりますが、一般的には7月上旬から中旬に贈られます。関東地方では7月初旬から15日まで、関西地方では少し遅れて7月中旬から8月初旬にかけて贈ることが多いとされています。
お中元の由来ですが、中国の道教の行事と仏教の盂蘭盆会が結びついたものと言われています。もともとは祖先の霊を供養するためのものであったものの、だんだんと感謝の贈り物をする習慣として発展し、現在に至ります。
お歳暮とは?
次にお歳暮についてです。お歳暮も、日本の伝統的な贈答文化のひとつとされ、年末にお世話になった人々に感謝の気持ちを伝えるために贈り物をする習慣のことを言います。お中元と同様、ビジネスでは取引先や上司などに贈られます。
送られるものとしては、食べ物や飲み物が中心で、年末年始に家族や友人と楽しめるような日持ちのする商品が選ばれることが多く、ハムや調味料、ビール、コーヒー、スイーツなどが選ばれますが、お中元より若干高額なものが贈られることが多いようです。
なお、お歳暮を贈る時期は、12月初旬から12月20日頃までが一般的ですが、関東では12月初旬から中旬に、関西では12月中旬から末にかけて贈ることが多いです。
お歳暮の由来ですが、年末に祖先や神々に捧げる供物が次第にお世話になった人々への感謝を表す贈り物に変わっていったとされています。
お中元・お歳暮の金額相場
ビジネス上の取引先や贈るお中元・お歳暮の平均相場金額ですが、一般的には「5,000円程度」とされており、なかには非常にお世話になっている方の場合「10,000円」を超えるようなものを贈ることがあるようです。ただ、あまり高すぎると逆に相手を恐縮させてしまうこともあるため、平均的な金額のものを選ぶのが無難といえるでしょう。
お中元・お歳暮のマナー
ビジネスでお中元やお歳暮を贈る際にはいくつかのマナーがあります。贈る側としてのマナーだけでなく、受け取った側としてのマナーも見られていますので、ここでチェックしておくと安心です。
お中元やお歳暮を贈る際にはのし紙をつける
のし紙とはお中元やお歳暮の商品に添える礼儀や感謝の意を表すための装飾用の紙のことを言います。もともと「のし」とは、贈答品に添えられる薄いアワビのことを指し、これが長寿や繁栄の象徴とされていたために贈り物に添えられるようになりました。現在は、印刷されたのし飾りが使われることが一般的です。
のし紙は水引のイラストに加え表書き(お中元やお歳暮などの目的を記載)、送り主の名前が書かれます。店舗から発送する際には印刷されたもので対応してもらえますが、持参する場合には、自分でのし紙を用意したうえで表書きや名前を書く必要があります。
なお時期によっては表書きの内容が変わることもあるため注意しましょう。
お中元の場合
「御中元(『御』は漢字にする)」7月15日ごろまで
「暑中見舞い」7月中旬を過ぎてしまった場合
「残暑見舞い」立秋(8月7日前後)を過ぎてしまった場合
お歳暮
「御歳暮」12月いっぱいまで
「御年賀」年明け1月7日の松の内まで
「寒中見舞い」それ以降
受け取った場合はお礼状を書くとベター
お中元やお歳暮は、本来であればお世話になっている御礼をこめて贈るものなのでお礼(お返し)をする必要はないと言われています。しかし、受け取った以上お返しをしなければと思う人は多いでしょう。とはいえ、必ずしもお中元やお歳暮をこちらからも贈るのではなくお礼状を書くだけでも十分気持ちは伝わります。
お礼状を書く際には、お中元やお歳暮が届いてから日が経たないうちに書くようにするのが基本です。また、電話でものが届いた旨を連絡するといった形でお礼を伝えるのもよいでしょう。
お中元やお歳暮のお礼状の書き方ですが次のような構成でまとめるとよいでしょう。
- 頭語:季節の挨拶や相手を思いやる言葉で始めます。
- お礼の言葉:贈り物に対する感謝の気持ちを伝えます。
- 相手の心遣いを讃える言葉:贈り物だけでなく、相手の気配りや心遣いにも感謝を示します。
- 近況や相手の健康を気遣う言葉:自分や家族の近況を簡単に伝えたり、相手の健康や繁栄を願う言葉を添えます。
- 結びの言葉:今後の関係継続を願う言葉や締めくくりの挨拶で終えます。
謹啓
梅雨も明け、暑さが一段と厳しくなってまいりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
この度はご丁寧なお中元を賜り、誠にありがとうございました。皆様のお心遣いに心より感謝申し上げます。いつもお気遣いいただき、本当にありがたく思っております。
暑さが一層厳しくなりますが、どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
謹白
拝啓
師走の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
この度は、結構なお歳暮の品を賜り、誠にありがとうございました。皆様のお心遣いに深く感謝申し上げます。早速家族で美味しく頂戴しております。
寒さが一段と厳しくなってまいりますが、どうぞご自愛くださいませ。貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
まずは、略儀ながら書中にて御礼申し上げます。
敬具
お中元とお歳暮両方送るべき?
お中元とお歳暮は両方贈るのが好ましいですが、それでも両方贈るのは手間もかかりますし、コスト的にも難しいということがあるでしょう。その場合には、年末に贈るお歳暮のほうを優先するようにするのが無難です。
お中元とお歳暮は贈り続けなければならない?
お中元やお歳暮は基本的に贈り続けることを前提で行うものです。長く付き合っていくことが見込める場合であれば贈るのが良い選択となりますが、一度だけの感謝を伝えるようなケースであれば、あえてお中元やお歳暮というかたちで贈る必要はありません。
途中で贈るのをやめてしまうと、相手を不安にさせたり(事業がうまくいっていないのではないか?など)、失礼にあたることもあります。突然やめて印象を悪くするよりは、まずはお中元をやめてみる、そのあとは年賀状のやり取りだけにする、といった形でやり取りを軽減していく方法が効果的です。