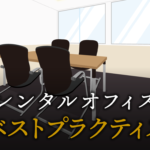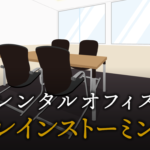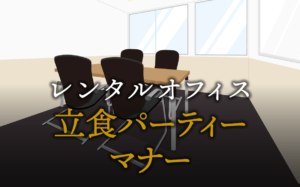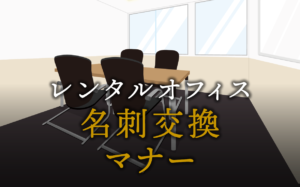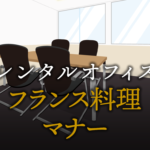贈り物に添える「熨斗(のし)」は、日本の伝統文化に根付いた大切なマナーのひとつです。慶事や弔事、季節の挨拶など、さまざまな場面で用いられる熨斗ですが、それぞれ適切な書き方や使い分けがあり、相手への気持ちをより丁寧に伝えるために熨斗の意味や用途を正しく理解することが大事です。
本記事では、熨斗の基本的な書き方からシーンごとの使い分け方までを分かりやすく解説します。これを機会に、大切な贈り物にふさわしい熨斗の選び方を学んでみましょう。
熨斗とは?
熨斗とは、贈り物に添えられる装飾のひとつで、贈る側の感謝や敬意、祝いの気持ちを表現するためにするものです。熨斗の起源は平安時代にまで遡り、当時は熨斗鮑(のしあわび)と呼ばれる干し鮑が用いられていました。ちなみに鮑は縁起物とされ、長寿や繁栄を願う意味が込められています。
現代の熨斗は、干し鮑ではなくこれを模した紙製の飾りが使われます。主に祝儀袋や贈り物の包装紙に印刷されたり貼られたりする形で使用され、儀礼的な意味を担っています。特に冠婚葬祭や年始や季節の挨拶などに用いられることが多く、贈り物をより丁寧な形で相手に届けるための大切な要素となっています。
熨斗の構成要素
熨斗の構成要素は、以下のようになっており、それぞれに特別な意味や役割があります。
表書き
表書きとは、熨斗の上部に書かれる文字で、贈り物の目的や内容を表します。たとえば「寿」「御祝」「御礼」「御見舞」など、用途に応じた言葉が書かれます。
水引
水引は、熨斗の中心に配置される飾り紐のこと。祝い事や弔事の性質に応じて結び方や色が異なります。
慶事用の場合は奇数が縁起が良いとされ、主に5本や7本が使われます。5本は最も一般的な本数で、結婚祝いや出産祝い、入学祝いなど幅広い場面で用いられます。一方、7本は格式を重視する際に選ばれ、特に結婚式や長寿祝いなど重要な慶事にふさわしいとされています。さらに格式を極める場合には9本や11本といった本数が選ばれることもあります。
一方、弔事用では偶数が選ばれ、4本や6本が用いられます。4本は「死」を連想させるため、弔事において適切とされる場合がある一方、地域によっては避けられる場合もあります。6本はより丁寧で正式な印象を与えるため、法事や香典返しなど格式を重んじる弔事に使われます。
熨斗飾り
熨斗飾りは、熨斗の右上または左上に配置される小さな飾り。もともとは熨斗鮑を模したものです。現在は紙製が主流ですが、喜びや縁起の良さを象徴しています。ただし、弔事では使用しません。
名前
熨斗の下部には贈り主の名前を書きます。個人の場合はフルネーム、企業や団体の場合は正式名称を記載します。複数人で贈る場合は代表者名を中央に書き、左側に「他一同」などを加えます。
熨斗の使い分け
熨斗は使用する場面によって異なる形式やマナーがあり、使い分けを間違えると相手を不快にさせてしまう恐れがありますので、注意が必要です。具体的には次のように使い分けます。
慶事用の熨斗紙
お祝いごとやおめでたい場面で使用される熨斗紙ですが、贈り物の内容や祝いの性質に合わせて、適切な水引の結び方を選ぶ必要があります。
蝶結び
「蝶結び」は別名「花結び」とも呼ばれ、繰り返しあっても良いお祝いに使用されます。たとえば、出産祝いや入学祝い、長寿祝い、お中元・お歳暮などがそれに該当します。蝶結びは何度もほどいて結び直せる形状で、「良いことが何度でも続きますように」という願いが込められています。
結び切り
「結び切り」は、「固結び」または「本結び」とも呼ばれ、一度きりで終わることが望ましいお祝いに用いられます。たとえば、結婚祝いや快気祝いなどがそれに該当します。結び切りはほどけにくい形状で、「繰り返したくない」という意味合いが込められています。
あわじ結び
あわじ結びとは、両端を引っ張るほど強く結ばれる形で、婚礼関係や快気祝い、格式の高いお祝いの際に用いられます。これには、「固く結び、末永く続く」という願いが含まれています。
弔事用の熨斗紙
弔事など、不幸があった際に使用される熨斗紙ですが、一般的には熨斗飾りを付けません。そして、「不幸が二度と繰り返されないように」という願いを込めて、結び切りが使用されます。水引の色は白黒または銀色で、弔事の性質によっては双銀(銀一色)の水引が使われる場合もあります。
仏事用の熨斗紙
仏教に基づく形式で贈り物をする際に使用される熨斗紙ですが、水引の色は白黒または銀色が基本で、表書きには「御仏前」「御霊前」「御供」などが記されます。なお、仏事の形式に従って適切に選ぶことが大切で、宗派によっては「御霊前」ではなく「御仏前」が推奨される場合があります。
季節の贈答用熨斗紙
お中元やお歳暮などの季節の贈り物に使用される熨斗紙ですが、何度でも続けたいという思いを込めて蝶結びが用いられるのが一般的です。表書きには「御中元」「御歳暮」などが書かれます。
熨斗のかけ方
熨斗のかけ方にはいくつかの形式があり、贈る目的や状況に応じて適切な選び方をする必要があります。
内熨斗
内熨斗(うちのし)とは、熨斗を包装紙の内側にかける形式のこと。内熨斗は、控えめな気持ちを伝えたい場合や目上の方に贈り物をするときに特に適しています。内側に熨斗をかけるため、贈り物を開けるまで熨斗が見えず、見た目の華やかさを抑えた慎ましい印象を与えます。
結婚祝いなどでは、内熨斗が選ばれることが多く一度きりのお祝いにふさわしい礼儀正しい形式として使われます。また、弔事の場合にも控えめな気持ちを示す意味で内熨斗が適切とされます。ただし、外見から熨斗が見えないため、贈る際に相手が熨斗の存在を認識できるような言葉を添える配慮が必要です。
外熨斗
外熨斗(そとのし)とは、熨斗を包装紙の外側にかける形式です。贈り物をより華やかに見せたい場合に用いられます。外熨斗は、熨斗が包装紙の上から見えることから、「お祝いの気持ち」や「贈る意図」を明確に伝えられるため、一般的なお祝いごとや会社間での贈答品に多く使用されます。
たとえば、出産祝いや入学祝い、お中元やお歳暮などでは、外熨斗が選ばれることがほとんどです。また、同等または目下の人に対して贈る場合にも適しており、贈り物の外見に気を配りたいときに効果的です。一方で、熨斗が包装紙の外側にあるため、運搬時に汚れたり破損したりしやすい点には注意が必要です。そのため、贈る前に熨斗がきれいな状態であるとしっかり確認することや、保護用の袋に入れるなどの注意が必要です。
仮熨斗
仮熨斗とは、簡略化された形式の熨斗を指します。具体的には、包装紙に直接印刷されているものや、シールタイプで貼り付けるものが主流です。カジュアルな贈り物や、大量に同じものを贈る場合に適しており、お中元やお歳暮で用いられることが多いです。
仮熨斗は、正式な場面にはあまり用いられませんが、日常的なお土産や手土産など、形式にこだわらない贈り物では十分役立ちます。時間や手間を省きたい場合に便利ですが、相手の立場や場面に応じて、より正式な内熨斗や外熨斗を選ぶべき場合もあるため、状況に応じた判断が求められます。
まとめ
熨斗紙は、贈り物に気持ちを添えるのに重要な要素ですが、使い方を誤ると相手に不快な思いをさせる可能性もあります。日頃の感謝を伝えるために、熨斗紙の基本的な知識を身につけておくことで、大切な贈り物にふさわしい心遣いを示すことができますので、恥をかかないように、日頃から注意しておきましょう。