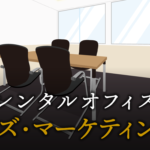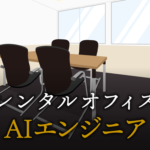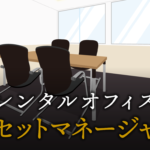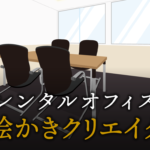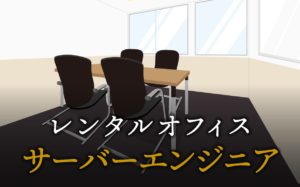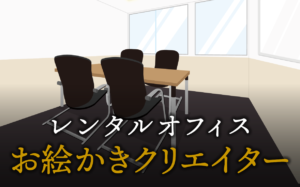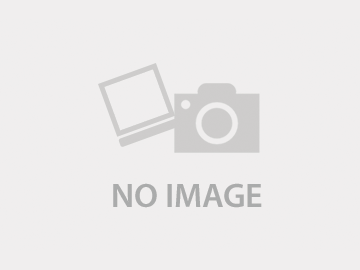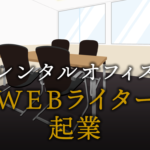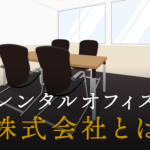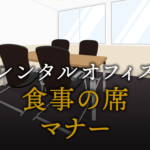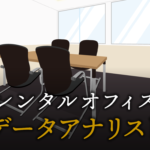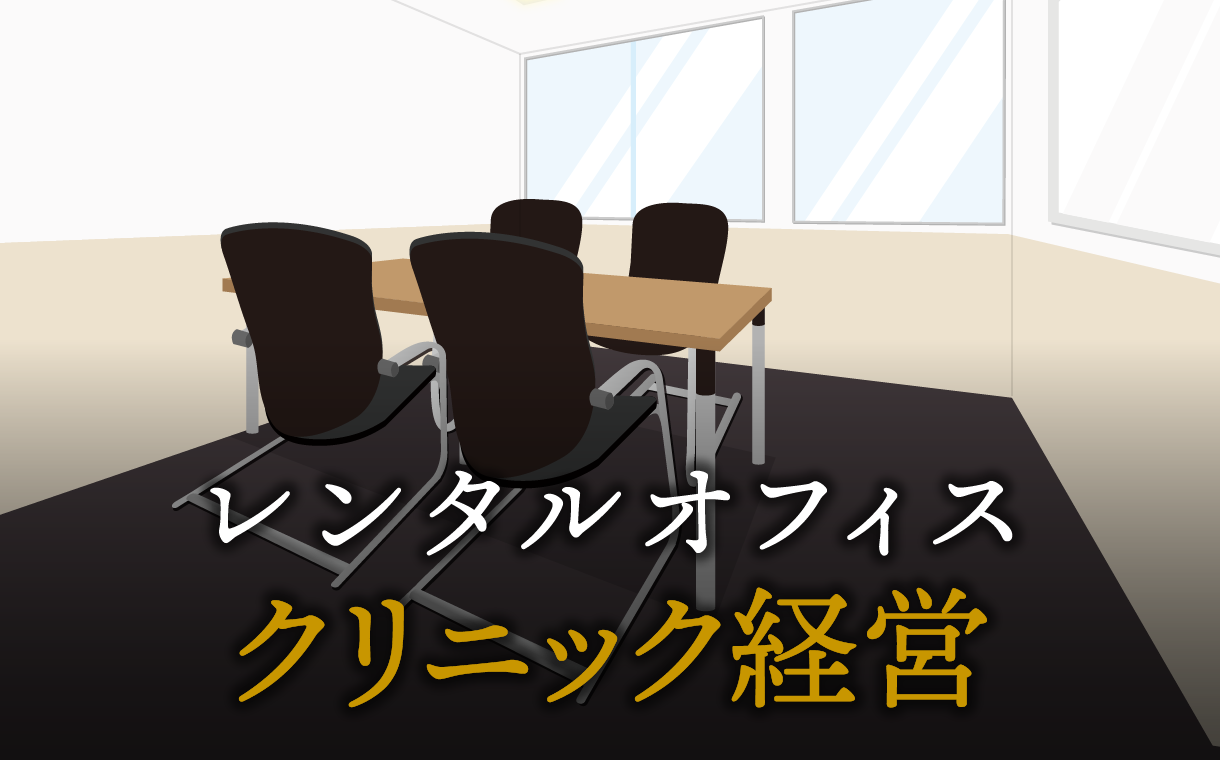
クリニック経営での起業は、医師としての専門性を活かしながら自らの理想とする医療を実現できる可能性を高めます。人によっては、地域医療への貢献や自由な診療方針の設定を行える一方、医療機器の導入やスタッフの確保、資金調達、法的手続きなど、経営者としての視点も求められるため、二足の草鞋を履く覚悟がないとできないかもしれません。
今回はクリニック経営で起業する方法について見ていきたいと思います。
目次
クリニック経営とは?
クリニック経営は、単に医療行為を提供するだけでなく経営者として医療機関全体をマネジメントすることが求められます。診察室の外では経営の視点が常に求められ、収益性・継続性・地域貢献の3つのバランスをとることが重要です。
なかでもクリニック経営では、患者数の確保が経営基盤となります。どれだけ質の高い医療を提供しても、クリニックが認知されなければ経営は成り立ちません。診療科目や立地選び、地域のニーズ分析は開業前から徹底して検討しなければなりません。
また、診療報酬制度の仕組みを理解し保険請求を適切に行うことも欠かせません。特に、レセプト業務や加算の算定には正確性が求められますし、収益に直結する部分でもあるため事務体制の整備が必要です。
さらに、クリニックには医療機器や薬剤の調達・維持管理、人材採用と教育、シフト管理、感染対策、広告・広報活動など多岐にわたる運営課題があります。診療が滞りなく行えるよう、バックオフィスを含む組織全体を最適化しなければなりません。
患者との信頼関係構築も重要で、医療サービスの質や接遇、待ち時間の工夫など患者満足度を高める取り組みがリピーターや口コミにつながります。
クリニック開業の流れ
ここからは一般的なクリニック開業の流れを各段階のポイントとともに詳しく掘り下げてみていきます。
開業動機とコンセプトの明確化
まず大切なのは、なぜ独立開業(起業)するのかという動機を明らかにすることです。単に収入を増やしたい、勤務医の働き方に不満があるといった動機だけでは途中で迷いやブレが生じやすくなります。
そのため、「子育て世代をサポートする小児科」「糖尿病治療に特化した内科」など、提供したい医療のスタイルや対象とする患者層を明確にすることで、内装やスタッフ構成、マーケティング戦略などすべての方針に一貫性が生まれます。理念がぶれないことは、患者やスタッフの信頼にもつながります。
市場調査と立地選定
開業地の選定は、経営の成否を大きく左右します。まずは、周辺の人口構成や競合するクリニックの数、診療科目などを徹底的に調査します。もちろん、自宅をベースに開業するケースもあると思いますので、その場合にはエリアは選べませんが、それでも地域の特性は理解しておく必要があります。
また、駅からの距離や車でのアクセス、近隣にスーパーや保育園があるかなど、患者の通いやすさについての調査も重要です。開業コンサルタントと連携することで、データをもとにした客観的な判断も可能です。
開業資金の調達と事業計画書の作成
クリニックの開業には最低でも2,000万〜3,000万円、場合によっては5,000万円以上の資金が必要とされています。これには物件取得費、内装費、医療機器、広告費、採用費、当面の運転資金などを含みます。
この資金をどう確保するかが最初のハードルであり、金融機関から融資を受けるためには、綿密な事業計画書の作成が必要です。計画書には地域特性を踏まえた市場分析、初年度の患者数見込み、月ごとの収支計画、数年後の収益見通しなどが必須。実現可能性のある数字と論理的な根拠が説得力を持つ鍵となります。
物件契約・設計・内装工事
医療クリニックは特殊な施設であるため、一般的なテナントとは設計が異なります。診察室・処置室・待合室の動線を明確に分け、患者のプライバシーを守るレイアウトが求められます。
さらに、高齢者対応のバリアフリー設計や感染症対策としての換気やゾーニングなども重要となります。それには医療施設の設計実績がある建築士に依頼するのが望ましいでしょう。
医療機器・什器の選定と購入
たとえば内科であれば、心電図、超音波、レントゲン装置、血液検査機器などが必要となるように、診療内容に応じて必要な機器は異なります。これらの医療機器・什器の入手方法は、新品だけでなく中古機器やリースといった選択肢もあります。初期費用を抑える一方で、保守契約や更新時期の見通しを立てることも忘れてはいけません。機器の設置には配線・排気など設計との連動も必要なため、内装工事との連携も重要です。
各種行政手続きの実施
クリニックを開設するには、管轄の保健所に「診療所開設届」を提出して構造基準の審査を受けます。加えて厚生局への「保険医療機関指定申請」、消防署への届出、医師会への加入申請など複数の行政手続きが必要です。
また、医療廃棄物処理業者との契約や防火管理者の選任など、法令順守の観点からも多くの準備が求められます。そのため、スケジュールに余裕を持ち開業日から逆算して着実に進めることが大切です。
スタッフ採用・教育
受付や看護師、医療事務などのスタッフは、クリニックの印象を大きく左右する存在です。クリニックの理念や接遇方針に共感し、柔軟に対応できる人材を選ぶことが重要です。
採用後には、業務フローやマナー、レセプト業務の流れなどを丁寧に教育し、開業前にロールプレイングやシミュレーションを通して動線の確認を行うと、トラブルが減らせます。人材が定着するかどうかも、安定経営の大きなカギとなります。
集患・広報活動の準備
どれだけよい医療を提供しても、クリニックの存在を知られなければ患者は来院してくれません。よって開業前から地域に向けた広報活動が必要です。
たとえば、チラシ配布や地域新聞、フリーペーパー掲載、Googleマップ登録、ホームページやSNS運用などデジタルと紙媒体の両面からアプローチします。患者との最初の接点を丁寧に作ることで、リピートにつながります。
開業と診療開始
クリニックの開業日を迎えたら、無理に予約を詰め込まず少数の患者対応で業務フローを確認しながら徐々に患者を増やしていくと安心です。予期せぬトラブルや患者の動線のズレなども起きがちなので、初動は柔軟に対応できるようにしておくと良いでしょう。
クリニックを開業した場合の収入
クリニックを開業した場合の収入は、診療科目、立地、開業規模、経営スタイルによって大きく異なります。
たとえば、内科や小児科などの一般的な保険診療を中心としたクリニックでは年収1,500万円~3,000万円程度が一般的な相場です。患者数が安定し、効率的な診療が行えるようになると着実に収益を上げることができます。一方、耳鼻科や皮膚科、眼科など比較的患者の回転率が高く診察単価が安定している診療科では、2,000万円~4,000万円とより高い年収が期待される傾向があります。
さらに、美容皮膚科や自由診療を中心とするクリニックの場合、施術単価が高く保険点数の縛りもないことから、うまく集患できれば年収3,000万円を超えるどころか年間で1億円を超えるケースも珍しくありません。
ただし、自由診療は広告費や人材投資がかさむほか、患者獲得に戦略的な仕掛けが必要なため、単純に高収益とはいかないのが実情です。
まとめ
クリニック経営には、医師としての専門知識を活かしながら自らの理念に基づいた医療を提供できるといった大きなメリットがあります。診療内容や働き方、スタッフ体制を自分で設計できる自由度が高く、地域に密着した医療サービスを展開することで安定した患者層や信頼を築くことも可能です。
ただし、クリニック開業には多額の初期投資が必要で、立地選定や集患対策、スタッフ採用・育成、経営管理など、医療と経営の両面でのスキルが求められます。よって専門性と経営感覚の両立が成功の鍵となります。