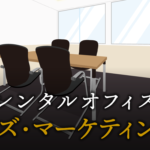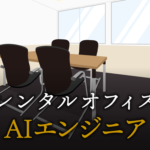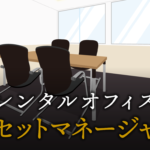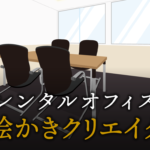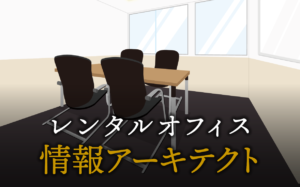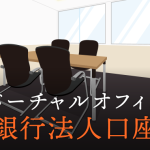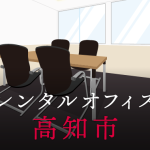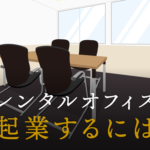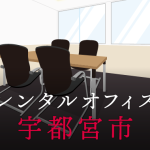変化の激しい現代において、ソフトウェア開発やビジネス現場において「アジャイル」という考え方が注目されています。顧客ニーズが常に変化する今、スピード感と柔軟性を持って開発・改善を繰り返すために用いられるアジャイルという手法は、多くの企業にとって成果を生み出す鍵となっています。
本記事では、アジャイルとはどういうものなのかについて詳しく解説していきます。
目次
アジャイルとは?
「アジャイル(agile)」という言葉の本来の意味ですが、「俊敏な」「素早い」「機敏な」といった身体的・精神的な素早さや柔軟性を指しています。ラテン語の「agilis(動きやすい、活発な)」が語源となり、人や動物が軽快に動く様子や状況に応じて柔軟に対応できることを意味します。
そこから発展して、ビジネスにおけるアジャイルは、「変化に柔軟かつ迅速に対応しながら、継続的に価値を創出するためのマネジメント手法」や「組織のあり方」を言います。もともとソフトウェア開発の手法として登場しましたが、現在ではマーケティング、人事、製品開発など、あらゆるビジネス分野に応用されています。
アジャイルのベースとなるのは、「顧客価値の最大化」「小さく始めて素早く改善」「チームの自律性」「変化を前提とする柔軟な思考」といった考え方で、たとえば長期計画を立てて一気に実行するのではなく、短期間のサイクルで試し、顧客の反応を見ながら軌道修正していくアプローチが特徴です。
アジャイルに関連する用語
アジャイルを使用する言葉としては、次のようなものが挙げられます。
アジャイル開発
「アジャイル開発」とは、IT業界でよく聞く言葉で、2001年に発表された「アジャイルソフトウェア開発宣言」に基づく開発手法のことを言います。従来のウォーターフォール型開発のように要件定義からリリースまでの流れを一括で行うのではなく、1~4週間程度の短いサイクルで設計・開発・テスト・レビューを繰り返す開発スタイルです。これにより、ユーザーからのフィードバックをすぐに取り入れられ、リリースまでの時間を短縮し、無駄な機能や手戻りを減らせるというメリットがあります。
アジャイルHR
アジャイルHRとは、人事制度や人材育成にアジャイルの考え方を取り入れる手法を言います。たとえば、年1回の評価や画一的な研修制度に代わって日々の対話や継続的なフィードバックを重視したりします。また、社員一人ひとりの強みや志向を尊重し、自発的な成長や学びを支援する環境づくりなども行われます。なお、アジャイルHRにより評価制度もチームやプロジェクト単位で柔軟に設計されるケースが増えており、人を管理するのではなく人が最大限に活躍できる土壌を整える方向へとシフトしていっています。
アジャイルマーケティング
アジャイルマーケティングは、IT業界やデジタルマーケティングの分野で使用される用語で、従来のように半年から1年かけて大きなキャンペーンを企画・実施するのではなく、短期間で小さな仮説検証を高速で繰り返すスタイルのマーケティングを言います。
市場の反応が読めない時代において、仮説ベースで施策を設計し、データを元に効果測定して即座改善を行うことにより、精度の高いマーケティング活動を可能にします。チーム内での情報共有や目的の可視化、役割の明確化をすることができるのが特徴です。
アジャイル思考
アジャイル思考とは、特定の方法論にとどまらず変化を前提とし、顧客価値を最優先に考えながら失敗を恐れずに試行錯誤を繰り返す姿勢のことを指します。個人やチームがアジャイル思考を持つことで、新しいアイデアを採択し、変化を脅威ではなく成長のチャンスとして捉えられるのが特徴です。
また、継続的な学習と自己改善を大切にし、結果よりもプロセスを重視する文化の醸成につなげることもできます。
アジャイルのメリット・デメリット
アジャイルは、100%万能な手法というわけではなく、組織の文化やチームの成熟度、プロジェクトの性質に応じて適切に取り入れる必要があるアプローチ手法です。その柔軟性ゆえに成果を出しやすい反面、一定の前提条件が整っていなければ逆効果になるリスクもあります。
アジャイルのメリット
アジャイルの最大のメリットは、変化に柔軟に対応できることに他なりません。ビジネスや開発現場では、当初の計画通りに物事が進むことは非常にまれで、市場の動向や顧客の要望は刻々と変化します。
アジャイルはその前提に立って最初から完璧を目指すのではなく、小さな単位で見せられるものをつくり、顧客のフィードバックを受けながら改善していくことに重きを置いています。その結果、本当に顧客にとって必要なものを、無駄を最小限に抑えつつスピーディに届けることができます。また、開発チームや関係者同士のコミュニケーションを密にすることで、チームの一体感や士気を高めることも可能です。
アジャイルのデメリット
一方で、アジャイルは最初にすべてを決定せずにプロジェクトを進めるといった性質上、ゴールが曖昧になりやすく、全体スケジュールや予算の見通しが立てづらくなることがある点がデメリット。特に、アジャイルに不慣れな組織や合意形成文化が十分でない場合には、「柔軟さ」が「場当たり的」な意思決定につながってしまう危険があります。また、顧客やステークホルダーが継続的に関与することが前提であるため、関係者の協力が得られない場合にうまく機能しないこともあります。
アジャイルの概念を導入する際に注意すべき点
アジャイルの概念を組織やプロジェクト等に活用する際に注意すべき点として、手法としてのアジャイルと考え方としてのアジャイルを混同しないことがあります。
たとえば、アジャイル開発において、「スクラム」や「カンバン」といった具体的な開発フレームワークばかりに目を向けると、プロセスの形だけをなぞってしまい、本来アジャイルが大切にしている価値観が形骸化してしまう恐れがあります。アジャイル導入を成功させるには、「なぜアジャイルを活用するのか?」という目的をチーム全体で共有し、その目的に沿って柔軟に手法を選ぶ姿勢が不可欠です。
また、アジャイルは全員参加型のアプローチであり、単に開発チームだけが変わればうまくいくというものではなく、プロダクトオーナーやステークホルダー、経営層なども含め、関係者全体の意識や行動が問われます。特にトップダウン型文化が根強い組織の場合には、意思決定のあり方や評価制度の見直しが必要となることもあります。
場合によっては、アジャイル導入によって既存の権限構造や上下関係が揺さぶられることもあるため、組織内での反発や混乱が起こりやすくなる点に注意しましょう。
なお、アジャイルは導入したらすぐに成果が出るという性質のものではありません。試行錯誤を繰り返しながら少しずつ改善していくプロセス自体が、アジャイルそのものであるため、「効果が出ない」と短期間で判断してしまい、従来の方法に戻ってしまうケースも少なくありません。そのため、長期的な視点で変化を受け入れ続ける覚悟が求められます。
まとめ
アジャイルは、変化の激しい現代のビジネス環境に柔軟に対応するための重要なアプローチであり、多くの企業がその導入に積極的に取り組んでいます。ただし、導入時には完璧を目指すのではなく、小さく始めて迅速に検証し、改善を重ねる姿勢が重要です。目的を見失わず、アジャイルの本質を理解しながら、柔軟に活用していきましょう。