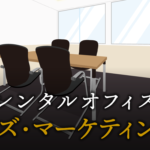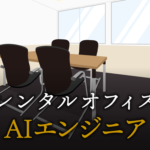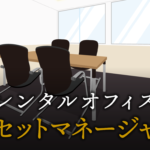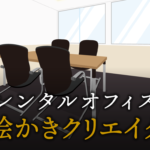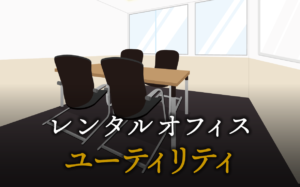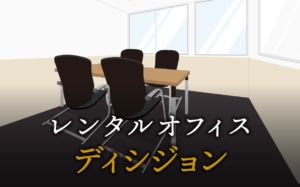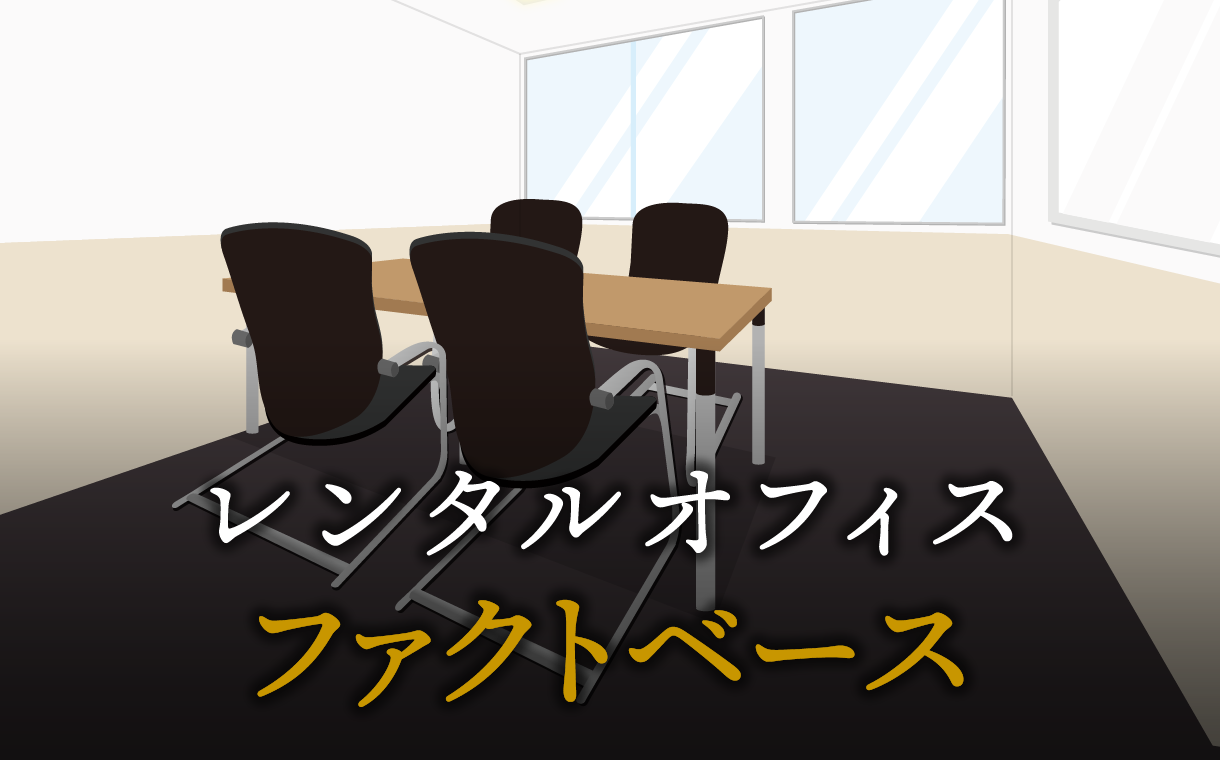
ビジネスや議論の場において、相手に対して説得力を持たせるために感情や憶測に頼らず「事実に基づく思考」を重視する姿勢が昨今求められています。そうした背景の中で注目されているのが「ファクトベース」という考え方です。意思決定や戦略立案において「何を根拠にそう考えるのか」が問われる場面が増えている今、ファクトベースの重要性はますます高まっています。
本記事では、ファクトベースとはどういうものなのかについて詳しく解説します。
目次
ファクトベースとは?
ファクトベースとは、意思決定や課題解決において感情や直感ではなく、「事実」に基づいて物事を考える思考の枠組みを指します。この場合における「事実」とは、売上やアクセス数といった数値データ、アンケートやインタビューなどの調査結果、議事録や契約書といった公式な記録など第三者が見ても客観的に確認できる情報であり主観的な「なんとなく」「そう感じる」ではなく、「なぜそう判断するのか」「何を根拠にそう言えるのか」といった問いに対し、明確な裏付けを持たせることがファクトベースの基本姿勢となっています。
ファクトベースの考え方は、ビジネスや政策立案、研究開発の現場で重視されており、論理的な合意形成を行う際の強力な武器となり得るもので、ファクトに基づいた議論は、感情のぶつかり合いを避けて冷静かつ建設的な対話を可能とします。なお、事実に基づいた判断については、あとで振り返った時に妥当性を検証しやすく、改善や再発防止にも役立ちます。
ファクトベース思考の具体例
たとえば、売上が下がっている原因を探る際にファクトベース思考を使ってみるとどうなるでしょうか?
多くの人の場合、「営業のやる気が落ちているのでは」「競合が値下げしたからだろう」といった推測を考えがちですが、ファクトベースで考えるとしたらまず数字に着目します。具体的には、過去3か月間の売上データを週ごとに分解し、地域別、商品別、担当者別にトレンドを可視化するなどをしてみます。すると、ある特定地域・特定商品だけが落ちているとわかり、「営業全体のやる気」ではなく「その商品の供給遅れ」や「その地域での競合広告の強化」が原因であることが明確になるといった具合です。
また、新規採用を検討する場面でもファクトベース思考が効果を発揮します。人手が足りないという現場の声が上がってきた場合には、「すぐにでも人を増やさないとまずい」と思いがちです。しかし、ファクトベース思考ではまず現状の工数分析から始めていきます。そして、各社員の稼働状況や時間の使い方、繁忙時間帯を洗い出し、「本当に人が足りていないのか」「無駄な作業や属人的な工程がネックになっていないか」を見極めていきます。
その結果、単純作業が多いことから業務効率化ツールを導入するだけで1人分の作業時間が削減できるとわかれば、コストを抑えた本質的な改善を実行できる、これがファクトベース思考です。
ファクトベースと似た意味の言葉
ファクトベースと似た意味の言葉はいくつかありますが、共通点や重なる思考アプローチを持つものとして、以下のようなものも知っておきましょう
エビデンスベース
ファクトベースと最も近い言葉として挙げられるのが「エビデンスベース」です。医療や教育、政策決定などの分野でよく使用され、経験や慣習に頼らずに科学的根拠(エビデンス)に基づいて判断する姿勢を指します。
ファクトが事実全般であるのに対し、エビデンスは検証可能な根拠という意味合いが強く、より厳密な証明やデータに基づいた行動が求められる点でファクトベースよりも一段階専門的と言えます。
ロジカルシンキング
ファクトベース思考と密接な関係があるものとして「ロジカルシンキング」があります。ロジカルシンキングは、論理的に筋道を立てて考えることを意味し、事実や前提を丁寧に整理したうえで結論を導いていきます。ロジカルシンキングも、ファクトベース同様に思い込みに頼らず、事実に基づいて因果関係を見出す姿勢が基本なので、ファクトベース思考とは切っても切り離せません。
データドリブン
データドリブンは、近年のビジネスやマーケティングでよく使われる表現で、データに基づいて意思決定を行う手法のことを指します。数字や統計などの客観的な情報を起点とする点ではファクトベース思考と近い考え方です。ただ、データドリブンはより大量かつ定量的な情報(アクセス解析など)を活用するイメージが強いです。
上記のワードはいずれも「感覚ではなく、事実や根拠に基づいて考える」という点でファクトベース思考と親和性があります。とはいえ、各用語には文脈による微妙な違いもあるため、上手な使い分けが必要です。
ファクトベースのメリット・デメリット
ファクトベース思考には多くのメリットがある一方、実践においては注意すべきデメリットも存在します。
ファクトベースのメリット
ファクトベースの最大のメリットは、思い込みや感情に左右されない冷静な判断ができる点が挙げられます。たとえば、会議での意思決定や経営判断など、立場や意見が異なる人たちが集まる場においては、感情論や経験則だけで話がまとまることはありません。しかし、具体的なデータや事実に基づいて議論することで、感情的な衝突を避けて建設的な方向に会話を導くことが可能となります。
また、問題解決の精度が上がるのもメリットのひとつ。たとえば、売上が下がったときに「営業がさぼっているからだ」と感情的に判断するのではなく、データを分析して「ある特定の商材だけが不調」「その商品だけ供給に遅れが出ていた」といった確固たる事実があれば、改善すべき対象が明確になるだけでなく対策も具体的となります。
さらに、再現性のある判断ができることも見逃せません。上司に説明する際、「なんとなくそう思った」というよりも「過去の数値から明らかにこの傾向がある」と言ったほうが、説得力も出て周囲を動かしやすくなります。
ファクトベースのデメリット
一方で、ファクトベース思考にはデメリットも存在します。
そのひとつとして、ファクトに依存しすぎることで判断が遅くなることが挙げられます。たとえば、すぐに意思決定が必要な場面で「データが揃っていないから決められない」となると、重要な機会を逃してしまいかねません。現場においてファクトが完全に揃うことはほとんどありません。ですから、判断にスピードが求められる場合、多少の不確実性を受け入れたうえで動く勇気が必要です。
また、ファクトに表れない価値を見落とすリスクもあります。たとえば、従業員満足度を数字だけで評価しようとすると、目に見えない不満や文化的な違和感が軽視されるかもしれません。数字では測れない空気といったものも組織運営には重要な要素です。
ほかにも、データや事実解釈にバイアスが入りうる点にも注意が必要です。ファクトは一見客観的に見えても、どのデータを使うか、どの視点から分析するかで結果が変わることがあります。自分がどんなにファクトであると言ったところで、その裏に恣意的な選択が入り込んでいることもあり得ることは知っておきましょう。
まとめ
ファクトベース思考は、論理的で納得性のある意思決定を可能にし、ビジネスの場では特に大きな武器となります。しかし、ファクトばかりを重視しすぎると、スピードや人間的な側面、直感の重要性を軽視することにもなりかねません。大事なことは事実を基軸にしつつ、事実だけでは動かせないこともあるといった現実を見て、バランスの取れた使い方をすることです。