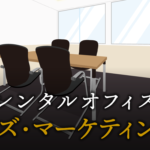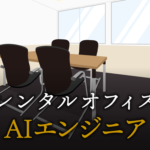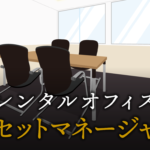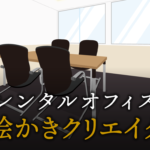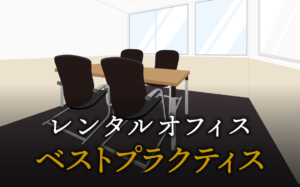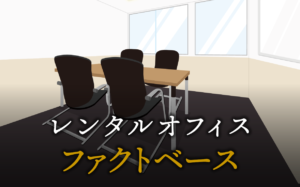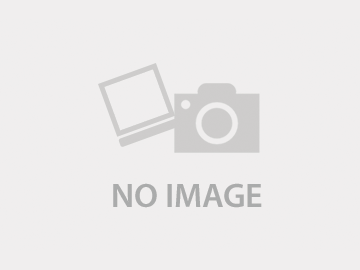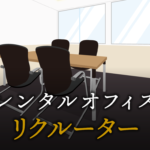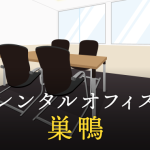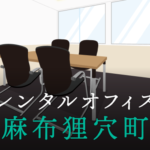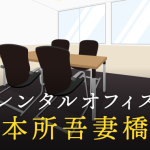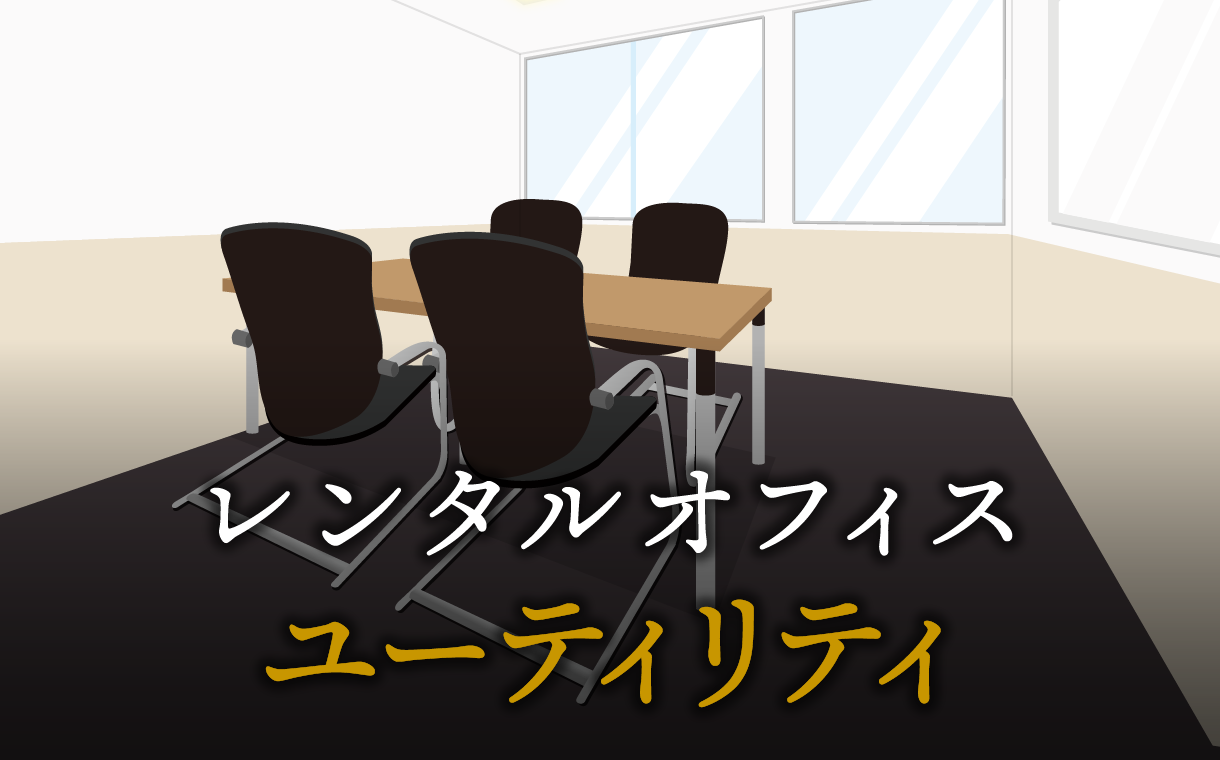
変化の激しい現代において、ユーティリティ性を持つ人材になることは、多様な価値を提供する上で不可欠な要素とされています。ユーティリティであること、つまりあらゆる状況に応じて柔軟に機能できる存在であることは、組織と個人双方にとって多くの面で恩恵をもたらしてくれることでしょう。
本記事では、そんなユーティリティについて詳しく解説していきます。
ユーティリティとは?
ビジネスにおける「ユーティリティ(utility)」とは、本来「有用性」や「役立つこと」を意味した言葉で、状況やニーズに応じて柔軟に価値を発揮する存在を指します。たとえば、複数の役割をこなす社員や、部門を越えて貢献する人材は「ユーティリティプレイヤー」と呼ばれ、組織にとって高い実用性と適応力を持つ存在として評価されます。また、商品やサービスにおいても、ユーザーにとってどれだけ利便性や効率性をもたらすかといった「価値の実感」もユーティリティと定義されることがあります。
ユーティリティであることのメリット
ユーティリティであることの最大のメリットは「変化への強さ」です。市場や組織の環境が目まぐるしく変化する現代では、特定の役割だけにとどまらず臨機応変にさまざまな業務をこなせる存在は組織全体に柔軟性と安定感をもたらします。
たとえば、人手が足りない部門を一時的にサポートしたり、新たなプロジェクトの立ち上げにスムーズに参画できたりと、常に今必要とされる場所で力を発揮できることは、非常に大きな強みとなります。
こうしたユーティリティな人材は、現場の潤滑油となれる存在として信頼されやすく、チーム間の橋渡し役としても重宝されます。その結果、組織の生産性が高まるだけでなく、自身の視野が広がり、キャリアの可能性も大きく広がっていきます。特定の専門分野にとどまらず複数の分野で経験を積めるため、汎用性の高い人材へと成長できるのです。
また、企業にとってはこのようなユーティリティな人材の存在がリスク分散にもつながることがあります。特定のポジションやスキルセットに依存しすぎることなく、状況に応じた人員配置が可能になることで、突発的な業務の変化にも柔軟に対応できる体制を作ることができます。
こうした点からも、ユーティリティであることは個人と組織の双方にとって大きな価値を生み出すと言えます。
ユーティリティと似た意味の言葉
ユーティリティに似た意味を持つ言葉には、用途の広さや実用性、柔軟性といった側面を含む表現がいくつか存在します。微妙にニュアンスは異なりますが、文脈に応じて置き換えたり、補完的に使ったりすることもできますので、これを機会に知っておきましょう。
汎用性
汎用性はユーティリティに非常に近い意味を持つ言葉で、特定の目的だけでなくさまざまな場面や用途に適応できる能力や特徴を指します。ビジネスにおいては、ひとつのスキルが複数の仕事に応用できること、あるいは人材や製品が複数領域で活躍できることを意味します。
多機能性
多機能性という言葉もユーティリティの性質を表す際に使われることがあります。多機能性は主に製品やサービスに対して用いられますが、「状況に応じて使える」「多様な用途に適応できる」といった意味合いを持っています。
会社でユーティリティプレイヤーになれる人の特徴
会社でユーティリティプレイヤーになれる人には次のような特徴があります。
たとえば、営業部に所属していながら顧客との契約書作成にも精通していたり、マーケティング的な視点で資料を組み立てられたりする人は、ユーティリティプレイヤーとなり得ます。また、プロジェクトリーダーとして全体をまとめる一方で、細かい事務処理や調整も自ら引き受けられるような人も、ユーティリティになれる素質を持っています。
また、ユーティリティプレイヤーになるには、人間関係構築力も欠かせません。ユーティリティプレイヤーは、他部署との連携や調整業務にも関わることが多く、誰とでも信頼関係を築けるコミュニケーション能力がかなり求められます。決して目立つ立場ではないかもしれませんが、組織の要所要所で力を発揮するため、社内での価値は非常に高いと言えるでしょう。
このような人々に共通するのは、自分の役割にとらわれない柔軟な姿勢を持っていることです。与えられた仕事だけでなく、今何が求められているかを自発的に考えて、自分の力をどう活かせるかを判断できる視野の広さを持ち得ています。また、変化を恐れず学ぶことに前向きであることも大きな特徴と言えます。新しい業務や慣れない領域にも抵抗なく飛び込み、周囲からの信頼を積み重ねていくことで、自然とユーティリティ性が磨かれていくのです。
ユーティリティであることのデメリット
ユーティリティであることは多くの場面でメリットを享受できる一方で、いくつかのデメリットも存在します。
まず「専門性が薄れる」といったデメリットがあります。幅広い業務に対応できることは強みである反面、特定分野での深い知識や高度なスキルを磨く機会が少なくなりがちです。そのため、「オールラウンドではあるけれど、尖った強みがない」という評価を受ける可能性も高く、職種やキャリアによっては不利に働くことがあります。
また「役割が不明確になりやすい」という問題もあります。複数の部署やタスクをまたいで活動するユーティリティ人材は、「何が本来の担当業務なのか」が不明確になりやすく、負荷が集中しやすくなります。特に都合よく使われてしまう状況が続くと、自分の時間が奪われたり、本来やるべきことに集中できなかったりといったストレスにつながることもあります。
「成果が見えにくく評価されにくい」といった点もユーティリティプレイヤーにありがちなデメリットのひとつ。ユーティリティな人は裏方やサポートに回ることが多く、目に見える実績や数字で評価されにくいポジションに置かれることが多いです。その結果として、昇進や給与などの面で正当に評価されないと感じることも多く、モチベーションの低下につながることがあります。
ほかにも、周囲から「頼めば何でもやってくれる人」として扱われることで断りづらくなったり、役割の境界線があいまいになったりするといったリスクも持ち得ます。自分自身のリソース管理や、ビジネス上の適切な線引きができないと、過度な業務負担に陥り疲弊してしまう恐れがあるので注意が必要です。
まとめ
ユーティリティな存在になれる人は、視野が広く、変化に強く、人との関係を大切にしながら、組織全体のために「自分が今、何をすべきか」を考えて動ける人です。そのため、ユーティリティであることは大きな価値がある一方、自分の専門性や働き方を意識的にコントロールしなければ、組織にとって単なる便利な人になってしまう危険性があります。万能であることが常に最善とは限らないことを常日頃から自覚しておくことが重要です。そんな中で、ユーティリティ性を武器として活かすには、自分の軸や限界をきちんと把握しつつ、バランスのとれた働き方を追求することが不可欠と言えるでしょう。